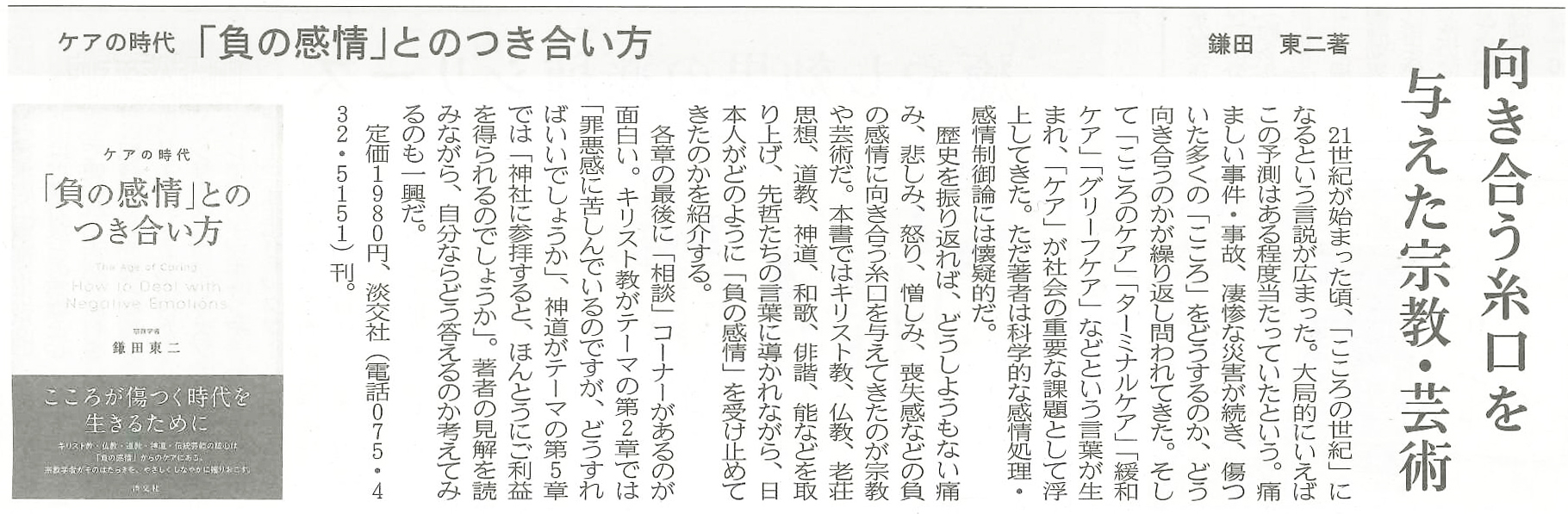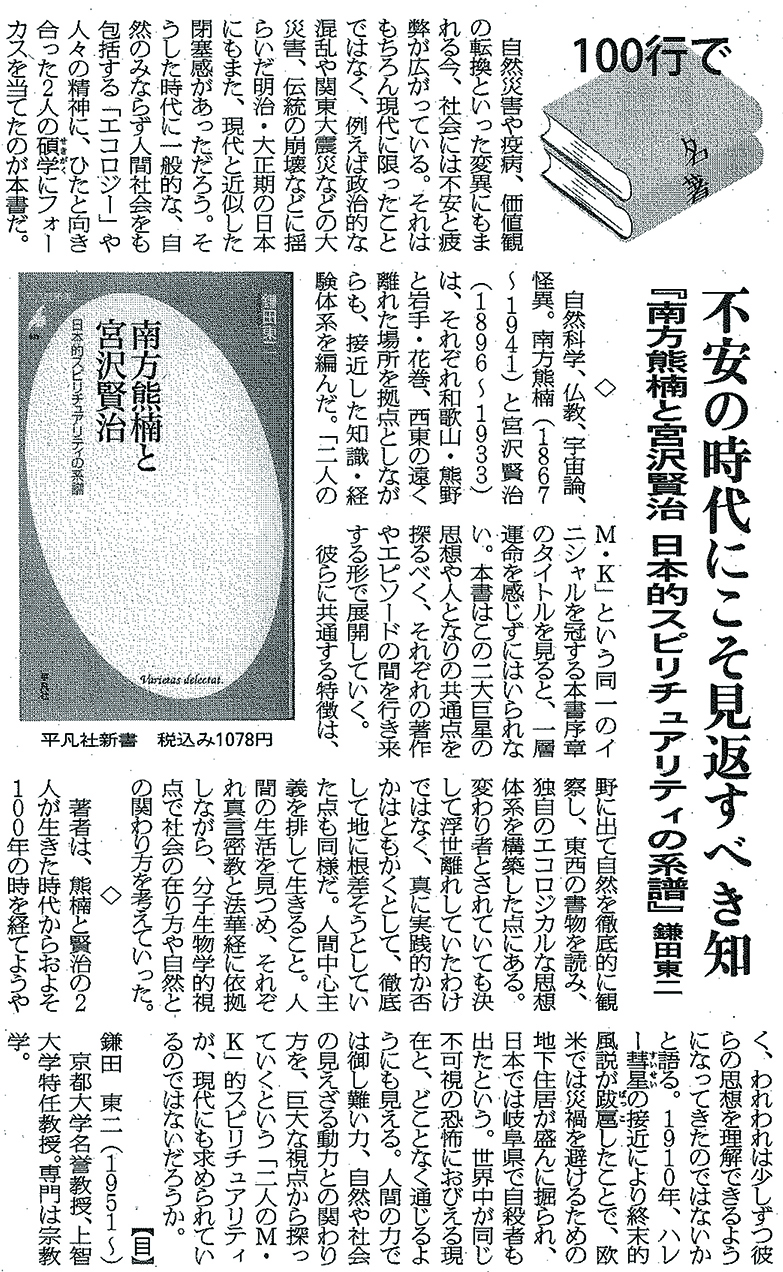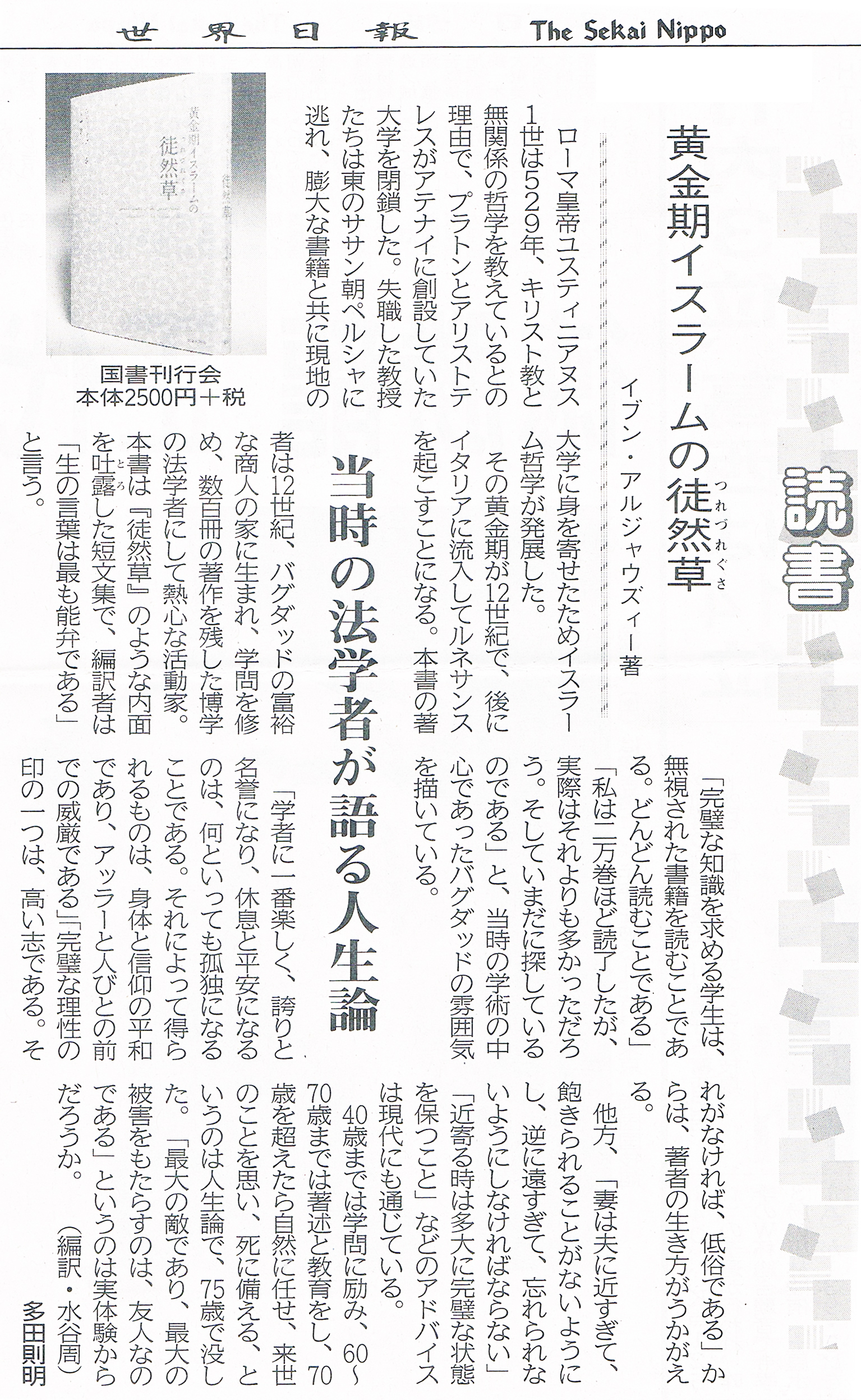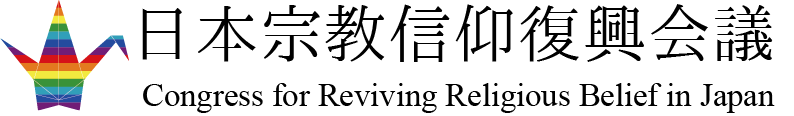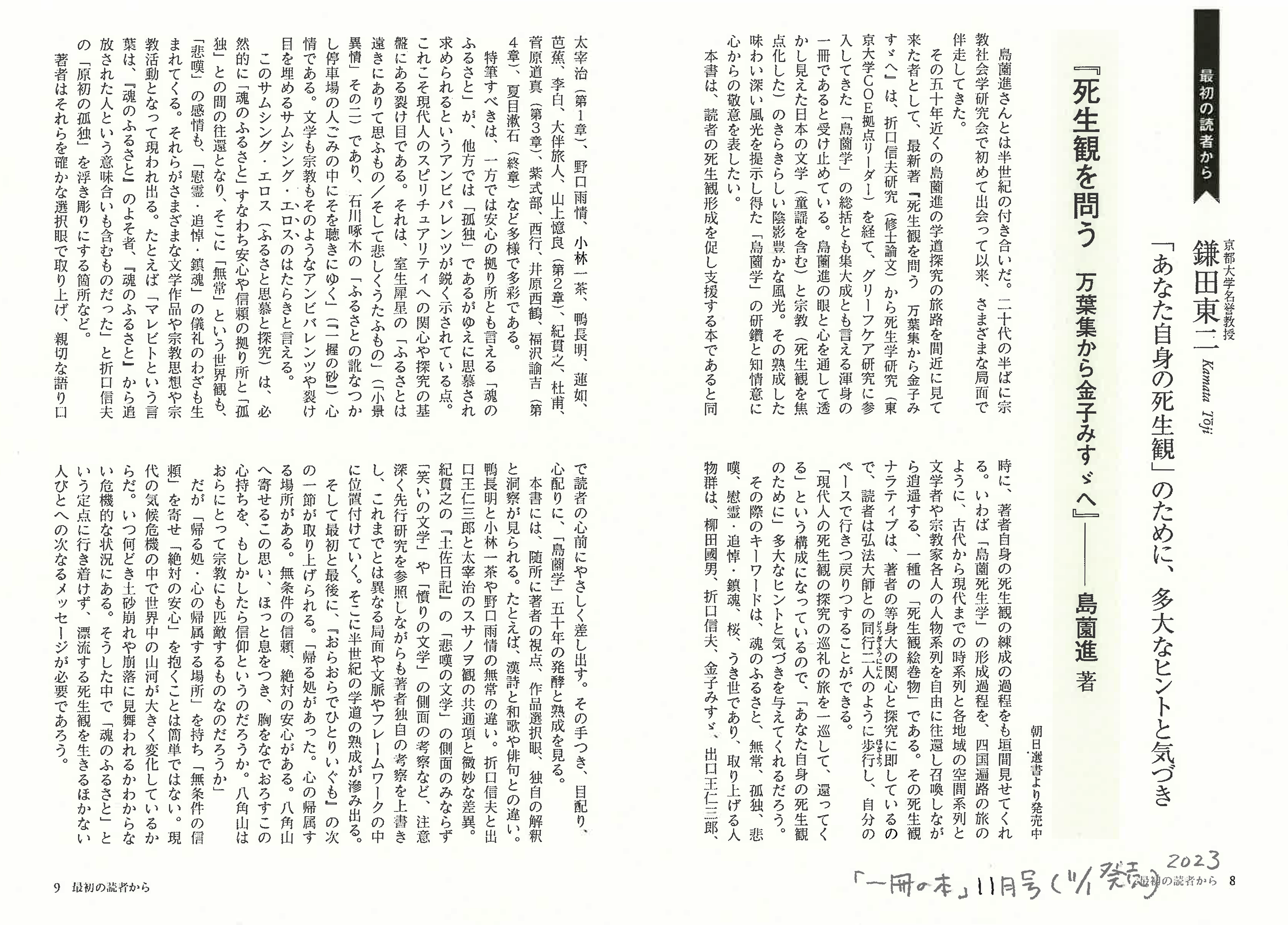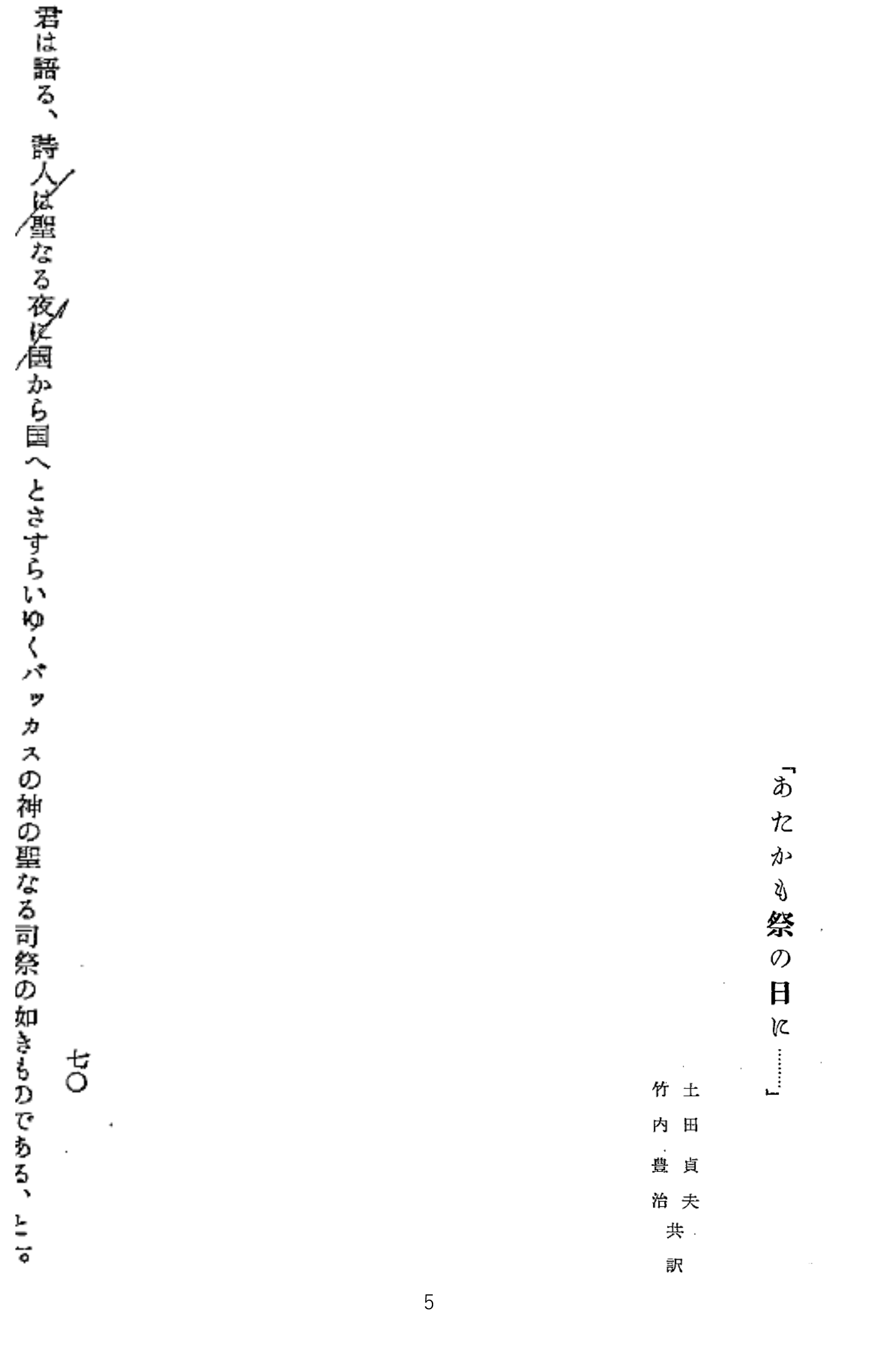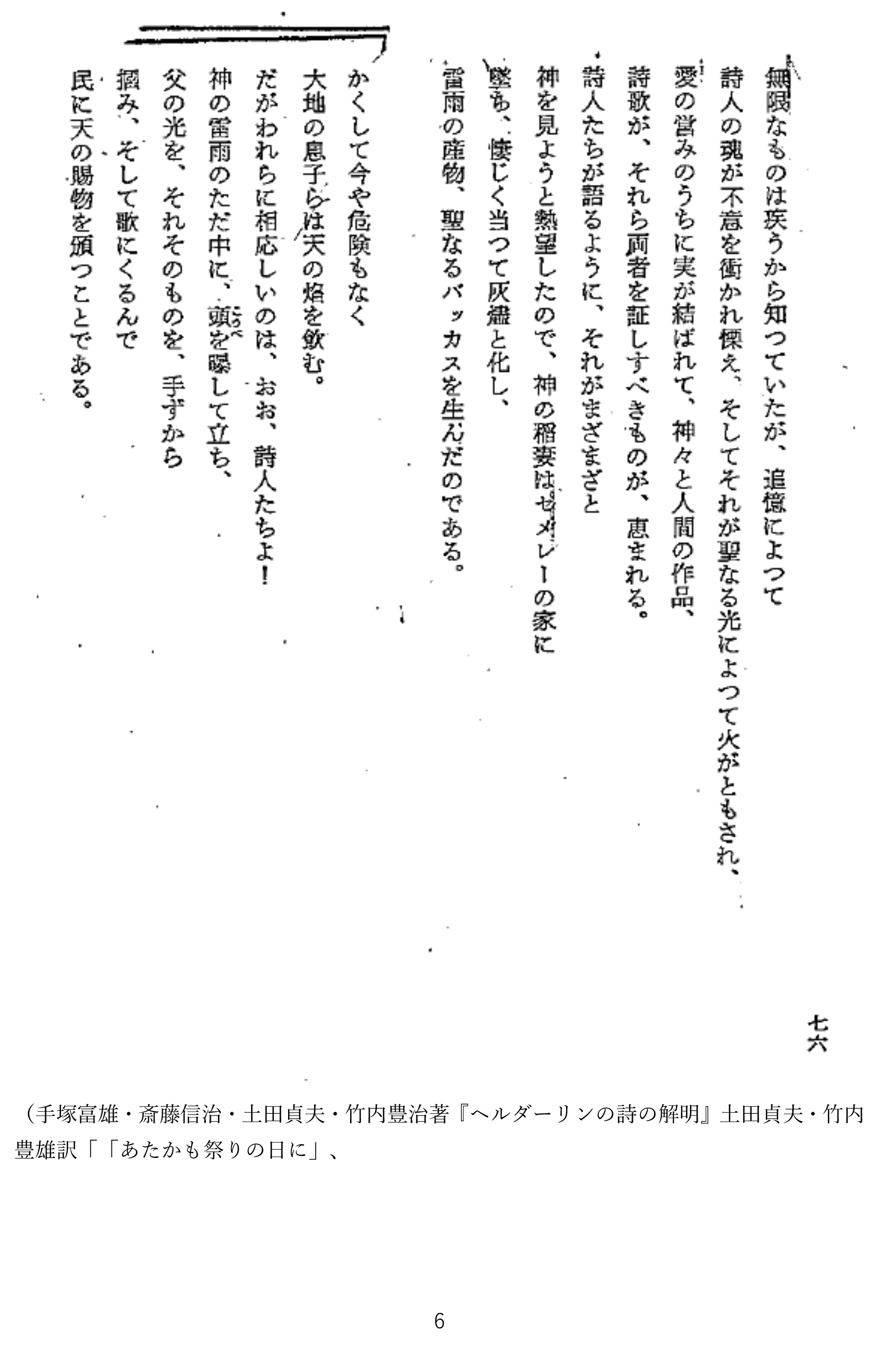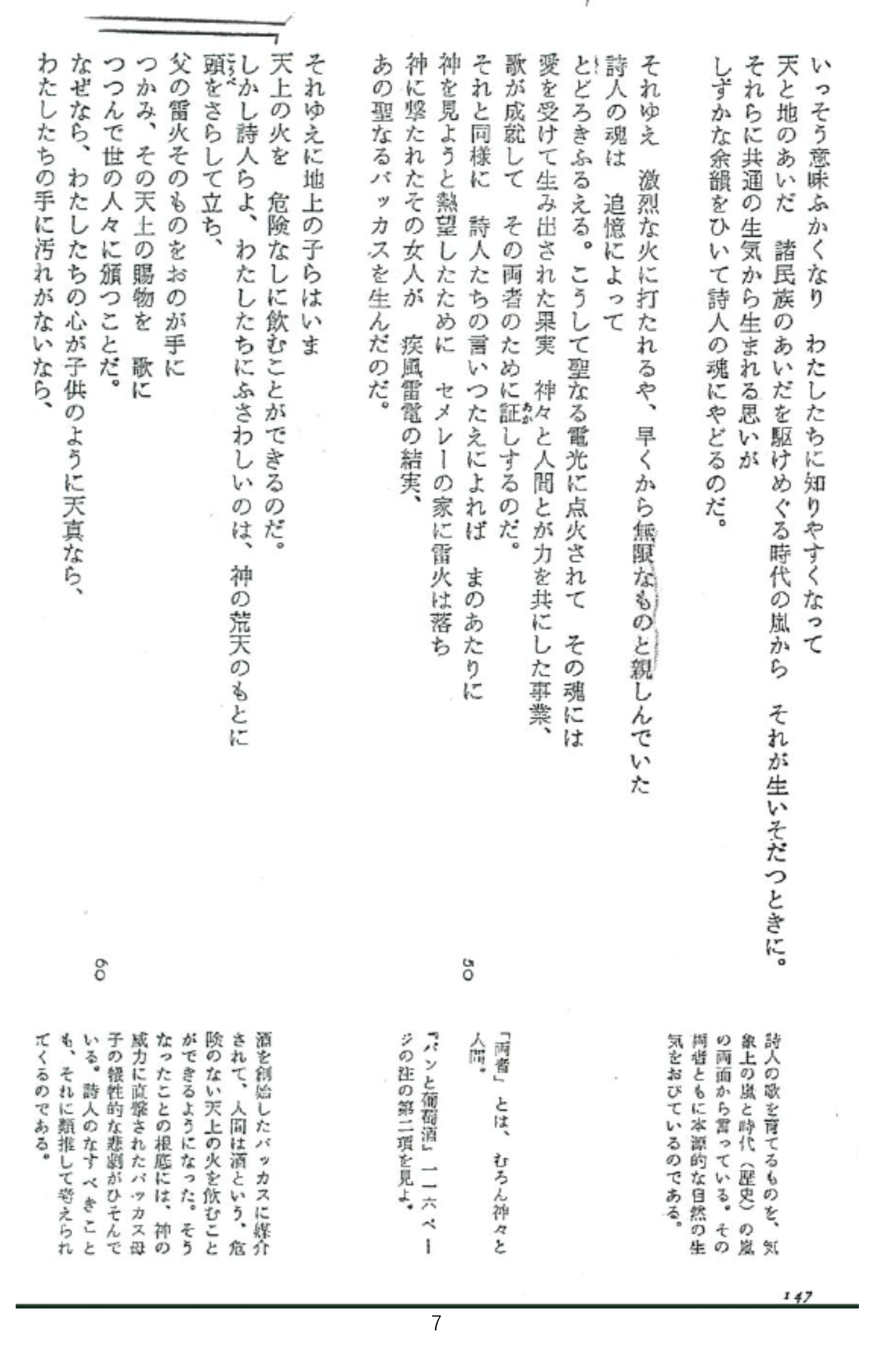藤井満著『京都大学ボヘミアン物語』あっぷる出版社、2014年1月30日刊 :鎌田東二 久しぶりに抱腹絶倒、大笑いした。
京大は「自由な学風」を謳う。その京大の中でもとびきり自由で、あほらしく、あほをすることに生きがいを感じているサークルが「ボヘミアン」というサークル。1984年に結成され現在も続いているという。
ということは、本年、結成40周年である。じつに長寿のサークルであるが、このサークルが「京都一の変態サークル」と言われているらしい(本書15頁)。
本書は、1985年に埼玉県立浦和高校から京都大学文学部社会学科に入学した「フジー」こと藤井満たちが卒業する1990年までに繰り広げるあほらしい活動報告。
メンバーは、
1期生(1984年入学、5名)。他に創設者の「教祖」と呼ばれていた1982年入学の「りょうさん」
2期生(1985年入学、9名)
3期生(1986年入学、7名)
では、そのどこが「変態」なのか? 一言で言えば、野蛮な冒険心、ということか。
徹底的なヒッチハイク
国内外でのサバイバル実験の旅
ボヘミアン節映画制作
恥かき「ボヘマラソン」
徹底切り詰め節約&酒飲み放蕩生活
「女人禁制」ルールの中の女性問題
などなど。とにかく、「あほ」なことをする。仲間をいじる。ふしぎな連帯感と愛をもって。 まずは、本書を読んでいただきたい。笑いをこらえながら。
ところで、著者の藤井満さんにおききしたい。
本書の売れ行きはいかほどでしょうか?
本書への反応(肯定的評価・賞賛など?)はいかがでしょうか?
知りたいものです。 2024年6月16日記
唐澤太輔×石井匠『南方熊楠と岡本太郎――知の極北を超えて』(以文堂、2024年6月14日刊) :鎌田東二 大変面白く、ほぼ100%納得できる対談集を読了した。
対談集は『南方熊楠と岡本太郎――知の極北を超えて』(以文堂、2024年6月14日刊)。
奥付では、これを執筆している明日の刊行だ。
ということは、刊行前に書評していることになる。
対談者は、唐澤太輔と石井匠。ともに、1978年生まれの同級生。因縁の同級生だ。それぞれに、10代‐20代に生きづらさの危機を抱え、それを南方熊楠と岡本太郎を読み込むことで乗り越えた。2人は、2人の先達であると同時に、「命の恩人」。
この対談集を読みながら、少し面映ゆかったが、同時に、さもありなんと納得した。唐澤は、南方熊楠に新鮮な読みを加えた中沢新一にインスパイアーされたことをくりかえし尊敬心をあらわに語り、石井は鎌田東二をいじりながら2度ほど「恩師」と述べている。
確かに、中沢新一と鎌田東二は、唐澤太輔と石井匠の因縁の関係と同様、同級生で、その学年は東大入試が全共闘ロックアウトで中止された因縁の学年(1968年度高校3年生)であった。
そんな些末なことは、本書の内容と何の関係もないと思う向きもあるだろうが、とんでもない。些末なことは大事なこと連関し、時に物事の結節点(南方熊楠の言う「萃点」)ともなるのだ。
対談者の2人は、取り上げる相方の
ファミリー
メソッド・メソドロジー・方法論
エロスとポリティックス
slime mold(粘菌)とJOMON(縄文)
未来可能性とリスポンシビリティ
を比較検討していく。そして、その双生児のようなの相似性を浮き彫りにする。そして、両者の中にある“神秘力”と“詩力”を明確に暴いた。これは、中沢新一と鎌田東二にも共通する部分であるが、中沢の方がさらに加えて「ロゴスとレンマ」力を駆使し、「神仏習合諸宗協働フリーランス神主」とか「ガン遊詩人」とか「神道ソングライター」とかと奇怪なことを騙る鎌田東二は「方便力」を駆使していると、付け加えることもできる。
ともあれ、本書は、めっぽうおもしろい。おもしろいから、ぜったい読んでみてくだチャイ!
それをいくら、論じても、詮無いから。
だが、一言、物足りないところを言っておく。2人とも、まじめすぎるよ! まっとうすぎるよ! もっとハチャメチャでもいいんだよ。もっとコワレテイテモ、イインダヨ!
もっともっと、「爆発」し、「四次元と対話」し(岡本太郎)、粘菌のように変形化(南方熊楠)してくだチャイ!
そして、もう1つ。「絶対感謝」(唐澤太輔の発言、232-233頁)という言葉。これは、先住民の動植物やいのちのやり取りに対する贈与的な存在感覚を言っているのだが、「絶対」という語にひっかかる。違和感があるのだ。
はたして、「絶対」という言葉が適切なのか? わたしの卒業論文の主査は仏教学者の三枝充悳(さいぐさ・みつよし)であったが、彼の口癖は「唯一絶対などはない!」という主張だった。これは、西田幾多郎の後期の著作に出てくる「絶対無」や西谷啓治の『神と絶対無』(弘文堂、1948年)に対する批判でもあったのかもしれない。
ともあれ、三枝充悳に倣って、わたしも「絶対」という言葉を用いることには慎重でありたい。そこで、わが「遺言」として出した『悲嘆とケアの神話学』(春秋社、2023年4月日刊)の「あとがき」には、唐澤の言う「絶対感謝」に近い表現を「複雑性感謝」と表現した。
それは、ケア論の研究の中から出てきた「複雑性悲嘆」に対する、それとは異なるもう1つの感覚の提示であった。キューブラ・ロスの『死ぬ瞬間』(“On Death and Dying”原著1969年)以来、死の受容過程を①否認→②怒り→③取引→④抑うつ→⑤受容、という五段階説がモデルないし批判の参照軸となり、「複雑性悲嘆(Complicated Grief:)」もその長枯れの中で出てきた学術的概念である。
2022年12月に大腸がんが発覚して以来、手術をし、それがステージⅣであることが判明し、脳にも転移し、主治医に「余命3年」と告げられても、ずっとわたしの中で「感謝」の念が強烈に維持されていて、それを「複雑性感謝」と名付けたが、そうした自分のいのち感覚、存在感覚からして、「絶対」という語を用いた「絶対感謝」という言葉は感覚的に支持できない。「絶対感謝」などという「絶対」の感覚や状態など、はたしてありうるのだろうか? すべては、相対・相依のうつろいのなかにあるのではないだろうか? そうした違和感である。
それはそれとして、唐澤太輔よ、石井匠よ、もっともっと、「爆発」し、「四次元と対話」し(岡本太郎)、粘菌のように変形化(南方熊楠)してくだチャイ!
『イスラームにおける直観の研究』(水谷周編著、森伸生著、前野直樹著)の紹介 :水谷 周 信仰に覚醒するのは、人の持つ直観の才覚に依っている。そこに直観研究の原点と意義が見出される。しかしいざそれは何かと問われると、直ちに即答は難しい。それほどに分かっているようで、不分明なものである。 本書はこの直観がイスラームにおいてはどのように把握され、解釈されてきたかを、古典と現代の文献に依拠しつつ可能な限り解明しようとしている。幾多の学識者の見解はもとより、原典であるクルアーンと預言者伝承における同課題の扱われ方についてもかなりの頁数を割いて整理、分析されている。
直観論をまとめれば、次のようになるだろう。全体を通じて見えてくるのは、クルアーンとハディースの教えを順守することに邁進する姿である。常に生活全体で取り組む中で、その人の「内なる声」に呼応し、神の鏡から映し出されるように、「心」に直観が働くのである。それは最も高貴な感性により、内在世界の頂点に達するごとくである。また直観のその先にある神からの特別な恩寵や祝福(超常現象)に慢心は許されない。それは段階的に継続する試練なのである。心の静穏と安寧をアッラーから賜り、自分の隅々までそれらが満ちることを感じることに、最良の果実が見出される。
なおこのようなほとんど突っ込んでは解析されてこなかった分野を明らかにすることは、宗教信仰を曖昧なままに温存しないで、共有される分析の光を当てる新たな試みといえる。それは信仰学確立の一端と位置付けられるものである。その意味では、本書の含蓄は狭い意味のイスラーム学だけではなく、宗教研究一般にも新たな一石を投じるものである。
新著『宗教と科学のせめぎ合いー信と知の再構築』の紹介 その5 :水谷 周骨子
宗教も科学も自信を喪失する時代に入っている。互いにせめぎ合ってきたが、それを互恵の関係に転じることができる。宗教はこれまで曖昧さが許されてきた局面に新たなメスを入れることで、情報の公開と共有性を高める必要がある(瞑想、悟り、祈りなど)。科学は心の内面にも対象を広げて、狭い意味の客観性を克服しないと、要素還元による人間の骸骨化は避けられない(気功学、身心変容技法の研究など)。双方共、新規まき直しである。このような検討の中、従来イスラームはほとんど蚊帳の外に置かれてきた。それが持つ比重に鑑みて、これも是正が必要である。
信と知の再構築のため、宗教も科学も新たな基礎が必要である。
宗教は日常的な行として、祈りを生活に取り込むべきである。悔悟、感謝、そして嘆願の気持ちである。精神の浄化と安寧の繰り返しである。そこからは、遺伝子レベルの効果が証明されており、修行僧は免疫性が高まっているという。また悟りや瞑想などをもっと情報化して、実証と共有が図られるべきである。それらが分かりにくいという主因は体験の共有が図られていないからである。その脈絡で、信仰をもっと宗教研究の認知された主要課題としてよいのではないか。
元来宗教が包括的であったものを近代化はそれをバラバラにして、人間を要素還元で骸骨化してきた。要素還元とは、不要と思われるものをそぎ落とす発想であるが、人間は水素、酸素、窒素などで構成されると捉えることなどで、思想や感情は不要な要素になる。非常に寂しい感覚。その均衡を復旧しないのは、科学一神教である。このような感覚に、誰でも気づいているが、気にしないことにしているに過ぎない。
科学は人の情動など内面も対象とすべきである。見えないものでも真実の世界は広く深い。不分明なテーマを扱う科学の試みは、着手されつつある。しかしまだあまり普及していない(気功学や身心変容技法(禅の実証研究、能楽の癒し効果研究)の研究など)。
さらに近代知の挑戦に対応して、進化論的啓蒙主義を克服する必要がある。新たな哲学が求められる。自然は共生に依存している(菌は植物に栄養素を提供)という知見に基づいた視点が必要(共生と言っても仏教由来の、従来パターンではない)。
以上は世界的な潮流だが、日本はさらに宗教アレルギーに見舞われている。それは戦前の国家神道と敗戦という史的因果関係のためであり、特殊な状況である。それを若い世代が認識できるかどうか。宗教に関する淋しい選択を再びしないよう、願わざるを得ない。
終わり
新著『宗教と科学のせめぎ合いー信と知の再構築』の紹介 その4 :水谷 周骨子
宗教も科学も自信を喪失する時代に入っている。互いにせめぎ合ってきたが、それを互恵の関係に転じることができる。宗教はこれまで曖昧さが許されてきた局面に新たなメスを入れることで、情報の公開と共有性を高める必要がある(瞑想、悟り、祈りなど)。科学は心の内面にも対象を広げて、狭い意味の客観性を克服しないと、要素還元による人間の骸骨化は避けられない(気功学、身心変容技法の研究など)。双方共、新規まき直しである。このような検討の中、従来イスラームはほとんど蚊帳の外に置かれてきた。それが持つ比重に鑑みて、これも是正が必要である。
信と知を統合するものとして、宗教における行を注視したい。そこでは身体的な動きを実施することで、雑念を払い、さらには脳裏を浄化することで、いわゆる赤子の心を取り戻す機会になっているのではないかと思われる。
ア.比叡山の千日回峰行 7年間で千日の間比叡山の峰々を回って読経と瞑想の日々を過ごす。2回にわたって9日間の断食、断水、不眠の荒行に臨み、それで生き仏になるとされる。満行の際には、阿闍梨という称号が与えられる。途中で下山することは許されず、常に自死のための小刀を帯同する。荒行が身体的にきついのは、初めの頃とされ、そのうち体が慣れてくると、むしろ心地よいものだそうだ。
イ.中世のエルサレム巡礼 エルサレム巡礼が阻害されているとして、12世紀末に十字軍の呼び掛けをローマ法王が発出した。それを受けて数世紀にわたって聖地奪還を目指した戦いが展開された。十字軍は軍事行動であったというよりは、一義的には宗教的な行であったと見なす方が良いかもしれない。少年十字軍は全員聖地には到達しなかったが、それでも時代の思潮を象徴していた。またベニス商人の暴利のために第4回十字軍は利用されたということが脚光を浴びがちだ。しかしそれも過大な十字軍募集をした指導者たちが十分に資金調達できなくなり、借金に悩んで商人たちの要望に従いイスタンブール侵攻となった。つまり自らが謀略をたくらんだのではなく、あくまで聖地巡礼を切望していた。
ウ.イスラームのマッカ巡礼 人生1回は実施する義務のあるマッカ巡礼は、現在では世界から400万人ほどが集まる。厳しいが憧れの行事である。巡礼月7日当たりから約1週間続くが、最高潮に達するのは9日午後のアラファ丘での留礼である。半日間、祈りを上げるのだが、その間悔悟と感謝と嘆願に時間を過ごす。その感激は著名な世界的旅行家イブン・バットゥータ初め、様々な巡礼記に記されてきた。
新著『宗教と科学のせめぎ合いー信と知の再構築』の紹介 その3 :水谷 周骨子
宗教も科学も自信を喪失する時代に入っている。互いにせめぎ合ってきたが、それを互恵の関係に転じることができる。宗教はこれまで曖昧さが許されてきた局面に新たなメスを入れることで、情報の公開と共有性を高める必要がある(瞑想、悟り、祈りなど)。科学は心の内面にも対象を広げて、狭い意味の客観性を克服しないと、要素還元による人間の骸骨化は避けられない(気功学、身心変容技法の研究など)。双方共、新規まき直しである。このような検討の中、従来イスラームはほとんど蚊帳の外に置かれてきた。それが持つ比重に鑑みて、これも是正が必要である。
近代知はさらに、何でも一端は破壊してみることから発想するという脱構築主義(ディコンストラクショニズム)や近代的啓蒙主義の発想を逆転しようという脱近代主義(ポストモダニズム)によっても挑戦を受けて生きた。特に後者は大きく強いものを選択する考え方ではなく、小さく弱いものを擁護し育成しようとする発想の転換を迫ることで、人権擁護や男女格差の解消などの具体的成果もあげてきた。また文化人類学は、部族社会と近代資本主義の成り立ちを、同等な俎板に乗せて比較、検討することで、価値観の逆転や遡行を余儀なくさせた。こういった近代知に対する挑戦は、本気であり、影響は避けられなかった。
宗教はと言えば、それは科学の挑戦を受けて来ただけではなかった。二つの巨大な挑戦に直面してきたのである。その一つが、物質主義、もう一つは宗教界自身の意気消沈という事態である。
物質主義は人間固有の価値を認めない考え方であるので、何とも淋しいものである。「人はパンのみに生きるにあらず」とは有名なイエスの言葉だそうだ。その意味解釈は異論があるとしても、平たく理解すれば、誰しも首肯できるところではないだろうか。「宗教は社会の阿片である」と言い切ったのはマルクスであったが、それが誤った人間理解に基づくことは、共産主義の崩壊が自らの手でその誤謬を証明したようなものであった。
こういう潮流を受けて、宗教界自身が今度は意気消沈となってきているのではないか。自信の拠り所が脆弱となり、はては瓦解し始めているのである。他方、あまりに目に余る過激な動向や、社会を愚弄するような迷信まがいも横行している。宗教こそは人間の究極的な価値を認めて、それを守り、広め、教化すべき立場にあることが、あまりにしばしば無視され、軽視されているのではないだろうか。宗教の個人的な救済に加えて、その社会的貢献についても改めて見なおされるべきである。
書評:『いのちの帰趨』鎌田東二 (佛教タイムス2023年11月16日)
「あなた自身の死生観」のために、多大なヒントと気づき(書評:『死生観を問う 万葉集から金子みすゞへ 』島薗進) :鎌田東二
新著『宗教と科学のせめぎ合いー信と知の再構築』の紹介 その2 :水谷 周骨子
宗教も科学も自信を喪失する時代に入っている。互いにせめぎ合ってきたが、それを互恵の関係に転じることができる。宗教はこれまで曖昧さが許されてきた局面に新たなメスを入れることで、情報の公開と共有性を高める必要がある(瞑想、悟り、祈りなど)。科学は心の内面にも対象を広げて、狭い意味の客観性を克服しないと、要素還元による人間の骸骨化は避けられない(気功学、身心変容技法の研究など)。双方共、新規まき直しである。このような検討の中、従来イスラームはほとんど蚊帳の外に置かれてきた。それが持つ比重に鑑みて、これも是正が必要である。
科学は実証の困難性が証明されて(カオス理論)科学者も戸惑っている。同理論では、無限に厳密な数値を方程式に入れること自体難しいとする(だから天気予報は難しいし、地震の予知は不可能とされる)。また1億回証明できても、1億1回目はわからないという素朴な疑問が、科学を困惑させ続けている。
宗教と科学はそもそも認識の方途が異なっているのである。だから双方がせめぎ合うのは的外れなので、それらは互いに他者としての互恵であるはずだ。双方の認識方法の異なることが基本にあるが、次のようなイスラーム学者(アフマド・アミーン、エジプト人、1954年没)の言葉がある。
「人には理性的な力以外にもう一つの能力、あるいは才覚があると思われる。それは既知の諸事実から結論を導き出す、論理でなじみのある方法ではなく、別種の真実を認識するものである。その力は、啓示や直観などの能力が潜んでいるところである。そしてそれは既知の事実の計算や、結果の評価はしない。それは一瞬の稲妻のようなもので、それで諸事実を明らかにするのである。動物にもそのような能力(本能)があることは、アッラーが言われたところである。」
他方、宗教が科学の成果によって、その妥当性に疑念がもたれ始めているのも事実である。特にそのような展開として、たとえば生物進化学では宗教はDNAによって左右されているといった主張や、脳科学でも宗教機能をコンピューターで解明しようとしてきている。人工知能AIの発達は、脳の機能を機械的に可能とするかもしれず、サイボーグの登場がささやかれている。それによって、神をも再現するかと噂され始めている有様である。
宗教信仰と科学の双方が、共にその基礎が瓦解し始めているかの状況が手に取るようである。しかしこのような人騒がせな問題は、多くの人は正面から正視しないで、日頃は座視しているのである。
終わり
新著『宗教と科学のせめぎ合いー信と知の再構築』の紹介 その1 :水谷 周骨子
宗教も科学も自信を喪失する時代に入っている。互いにせめぎ合ってきたが、それを互恵の関係に転じることができる。宗教はこれまで曖昧さが許されてきた局面に新たなメスを入れることで、情報の公開と共有性を高める必要がある(瞑想、悟り、祈りなど)。科学は心の内面にも対象を広げて、狭い意味の客観性を克服しないと、要素還元による人間の骸骨化は避けられない(気功学、身心変容技法の研究など)。双方共、新規まき直しである。このような検討の中、従来イスラームはほとんど蚊帳の外に置かれてきた。それが持つ比重に鑑みて、これも是正が必要である。
宗教と科学の関係は、一様ではなかった。キリスト教は科学と対立的な場面が多々生じてきて、敵対的にもなった。「それでも地球は動く」と訴えたガリレオ・ガリレイは聖書を誤解させたとして裁かれたことは、あまりに有名だ。最近でも英国の宇宙物理学者スティーブン・ホーキングはローマ法王に対して、神が不要となる可能性を示唆して騒がれた。
他方、仏教は宇宙存在を観察して、生々流転の観念を生み出して、それは信仰とは対立はしなかった。存在を客観視するのはキリスト教と同様であるが、自分自らをその存在の一部として位置づける点が異なっていた。だから無我の境地が強調される。しかしこのような境地からは、仏教科学は生み出せなかった。
残る三大宗教の一つである、イスラームは理性もアッラーの創造と説かれ、したがって科学は発達しても対立関係は生じなかった。新発見は常にアッラーの偉大な能力を改めて称賛するきっかけとなったのであった。しかしそれも結局事実の客観的追求という面においては弱みがあり、イスラーム科学は陰ることとなった。
以上は三大宗教と科学の関係のまとめであるが、そこで見逃せないのは、イスラームを検討の対象に入れたということである。イスラーム学は別として、従来一般的な課題についてイスラームの立場や見解が斟酌されることはまずなかったと言える。その最大の原因は、イスラームは日本ではまだまだ知られていない新参者であるということだ。ところが世界は変わっている。総人口の4分の1以上は、イスラーム教徒になりつつある。その数量的な増大は声の大きさになり、また以上に見たように独自の事実を提供しているという意味で、質的に看過すべきでない時代となっているのである。ただ教養や趣味としてイスラームを知るというのではなく、日本の世界認識というレベルにおける刷新が必要となっていることを確認しておきたい。
「信仰からの訴え」―その4(全4回) :水谷 周骨子
敗戦後もほぼ80年目を迎えようとしている。いわゆる「近代化」に精勤に励んだ結果が、今日の日本である。それは宗教的に誠に淋しい姿である。筆者は本年5月に『信仰は訴える』(国書刊行会)という一書を公刊した。その中で訴えたのは、4点あった。「信仰の訴え」の第四は、前述の種々の訴えが、どのような次世代に継承されているかという側面である。そのみずみずしい姿を改めて提示し、確認しておくこととする。
本書では、合計5名のイスラーム信者に登場してもらって、かれらの信条を吐露することで、いわば生の声を掲載した。それがあらゆる議論や陳述よりも、生々しい姿を世に訴える効果があるからだ。それは次世代への継承という側面を描くことにもなっている。この意図は見事に実現されたと評価できる。以下は、それら諸論考の中でも、極めつけと見られる個所の抜粋である(本書内で筆者名は記載されているが、ここでは内容をくみ上げることが目的であるので、それは控えることとしたい)。
A.原稿
「生きる意味」への関心が高まった。もしも、自分が生きていることに明確な意味があるとして、それを理解できたなら、この先も経験し続けるであろうこのやり場のない罪悪感を超えて、胸を張って生きていける気がした。・・・
ムスリムとは、「大切な自分自身を丸ごとアッラーに委ねる人」といった意味である。当時の私の感覚では、「生涯ムスリムとして頑張ります」とアッラーに宣言することは、喜ばしいことでしかなかった。・・・
悲しみとの向き合い方に関するものである。人間の心には容量があり、限界が来ると溢れてしまう。一方でアッラーとは、無限の懐の大きさを持つ存在である。イスラームは、小さな人間が抱くには大き過ぎる悲しみを、何よりも大きなアッラーが預かってくれることを教えている。どんな時でもアッラーが共に在ることを確信すればこそ、私は安心して、悲しみとさえ対峙できる。そして、いつか遠くの誰かの悲しみを癒す力になれる可能性を信じて、「アッラーに生かされている者」としての責任を果たすために努力できる。
B. 原稿
そして人間のデザイナーがアッラーなのです。つまり人間がいることが、アッラーがいる証拠になっているのです。・・・
そして因果サークルの外にいるのがアッラーなのです。アッラーには原因がないからアッラーなのです。それがアッラーの定義なのです。
C. 原稿
ただいまという感覚、ここが私の居場所と感じたからという言葉にならない感覚だったのだ。・・・カアバ殿を、魂を込めて巡る。どの国で生まれようがここで共に歩いている人々は家族のようなもの。ぎこちなさも感じない。私はムスリムだ。圧倒的な存在のカアバ殿の前で極めて自然にそこにいた。・・・
カアバ殿の周りを巡るタワーフをし始め三週目だったか、記憶していた何十もの願い事が一瞬で私の記憶からすべて消えた。思い出そうともひとつも浮かばないのだ。その代わりにムスリムにしてくれたことへの感謝と(小巡礼をさせてもらえた)ここへ来させてもらえたことの感謝に入れ替わった。それは私の意志ではなく脳の中を誰かに掃除されたかのようだった。・・・ 無宗教の日本人が私のようにピンと来て入信することも増えるだろう。日本人だからこその試行錯誤して生きていくことは神からのご褒美。その経験を踏まえて、イスラームを知らない人の感情に心を寄せ、独りぼっちにさせない優しいイスラームが伝えられたらと願う。
D. 原稿
知れば知るほど、真理探求を志して以来ずっと描き続けてきた「本物の宗教」のイメージと、イスラームが合致するのに目を見張ったのである。冠婚葬祭忘れたころの神頼みが常識とされる日本で生まれ育ちながらも、「本物の宗教なら、人間の生涯全てを左右すべきものであるはずだ」という思いは揺るがなかった。だからこそ出家に憧れたわけだが、家族という天与の絆をあえて断ち、人恋しく思う寂しさも全ては煩悩と罪悪視して一切の欲を滅しようと努める修行の道はかなわなかった。ところが聖と俗を分けないイスラームなら、無理なく日常の生活を送りながら、信仰の道を深めることも可能であるという。これこそ一日二十四時間、一週間七日という人生の全てを左右する本物の宗教だと得心したわけである。・・・
聖と俗を分けないイスラームには、職業的聖職者は存在しない。あるのは、教育的指導の責任を担う学者であり、伝教の責務は信徒各人に境遇に応じて負わされている。
E. 原稿
サラマ先生のクルアーン朗唱は決して、美しい節回しで聞かせるというようなものではありませんでした。とてもシンプルで、一語一語聞きやすい朗唱でした。それを聞いている間に、私に何かが起こったのです。言葉で説明するのは大変難しい。イメージで言うと、雲の間から光がさしてきて、自分とつながったと言いましょうか。これは真実だ、という思いが胸に広がりました。正直、そのあとサラマ先生の授業がどんなふうだったのか、その日どうやって自宅に帰ったのか、まったく覚えていないのです。
終わり
「表現としての学問」の実現 身をもって披いた新たな日本神話世界(書評:悲嘆とケアの神話論 須佐之男と大国主・鎌田 東二) :鶴岡 賀雄
鎌田東二第七詩集『いのちの帰趨』(港の人、2023年7月22日刊)について :鎌田 東二骨子
第7詩集『いのちの帰趨』を、「久高オデッセイ三部作」監督の故大重潤一郎監督(1946年3月9日生‐2015年7月22日没)の命日の日に合わせて出版した。
これまで、詩集(のようなもの)は合計8冊出している。順番に挙げていけば、次のようになる。
1,『水神傳說』泰流社、1984年1月1日刊(筆名:水神祥、SF神話詩小説、あらまき賞新人賞受賞)
2,『りしゅのえろす』メタモルフォーゼ社、1984年7月7日刊(筆名:きふねみづほ、全ひらがな詩集)
3,『阿吽結氷』夜桃社、1984年10月10日刊(筆名:水神祥、石川力夫との二人句集)
4,『常世の時軸』思潮社、2018年7月17日刊
5,『夢通分娩』土曜美術社出版販売、2019年7月17日刊
6,『狂天慟地』土曜美術社出版販売、2019年9月1日刊
7,『絶体絶命』土曜美術社出版販売、2022年5月30日刊
8,『開』土曜美術社出版販売、2023年2月2日刊
9,『悲嘆とケアの神話論―須佐之男と大国主』春秋社、2023年5月3日刊
10,『いのちの帰趨』港の人、2023年7月22日刊
10冊の内、1から3までは、1984年、わたしが32歳から33歳にかけての時に刊行した。この前後が自分にとって大きな転換期だったということになる。
しかし、出したものはすべてペンネームであるので、本名で出すことを嫌がっていたということになる。「水神祥」というペンネームは、『水神傳說』を出すために作ったものだから、難しく言えば「虚実皮膜」、ありていに言えば、忍者風に身をやつしたかったのだろう。
とにかく、20代には「水神傳說」を書き終えて出版しなければ死んでも死にきれないと思っていた。当時、一番執念を燃やしていた作物である。中身については、関心があれば読んでほしいというほかない。かなり変わった作物だと自分でも思う。
それを出して、「詩」について、一つの区切りを付けていたのだが、30代後半に友人を見舞うために50曲くらいの歌の作詞作曲をして、テープ録音して届けたことがある。これが、1998年12月12日から始まった「神道ソングライター」の活動の布石となっている。その時、わたしは47歳、前年には埼玉県大宮市(当時)の大成中学校のPTA会長をしていた。
なぜか、わたしに突然PTA会長の就任を依頼しに来た大成中学校の校長に、「運動会で法螺貝を吹いていいならPTA会長を引き受けてもいい」と返答し、「いいよ~!」と反応してくれたので、PTA会長に就任したのだが、就任して間もなく、神戸の連続児童殺傷事件(酒鬼薔薇聖斗を名乗る少年A事件)が起こった。少年Aは息子と同学年。Aの両親も我々夫婦とほぼ同学年だった。
阪神淡路大震災と少年Aの事件がきっかけとなって、喜納昌吉さんからの呼びかけをきっかけにして、当時神戸在住の大重潤一郎さんと一緒に神戸のメリケンパークを市から借りて「神戸からの祈り~満月祭コンサート」(1988年8月8日、「888」のゾロ目の日に開催)を実施し、さらに同年10月10日(平成10年10月10日、「101010」のゾロ目の日)に鎌倉の大仏様(高徳院)の前で「東京おひらきまつり」を実施し、その2ヶ月後に「神道ソングライター」として活動を始めたのだった。
そして、その時期に、後に、『常世の時軸』に収めることになる奇怪な散文詩が大量に自動書記のように生まれてきたのだった。「神戸からの祈り」の準備をしている最中、突然、詩が下りてきて、布団の中にワープロを引っ張り込み、掛布団を被って、布団の中でその奇妙な散文詩を打ち出し、それをFAXで実行委員会のメンバーに送りつけた。
朝早くから、実行委員長である鎌田東二のじつに不穏な変な詩を読まされる実行委員のメンバーはたまったものではなかっただろう。というよりも、不気味で、怖かったのではないだろうか? わたしも、どうすることができず、流れゆくまま、「犬も歩けば棒に当たる=捕らぬ狸の皮算用=トラタヌ人生」の真っ最中であった。
古希70歳が迫って来た67歳の夏、7月17日、天河大辨財天社の例大祭の日に合わせて、『常世の時軸』を出し、それに続く『夢通分娩』も、CDのサードアルバム『絶体絶命』も、天河神社の祭日である「7月17日」に刊行した。『狂天慟地』は「9月1日」なので、関東大震災の日に合わせ、『開』は天河大辨財天社の特殊神事「鬼の宿」に合わせ、『悲嘆とケアの神話論―須佐之男と大国主』は憲法記念日に合わせ、そして、『いのちの帰趨』は大重潤一郎さんの命日に合わせた。多くの作物は、ほぼ何らかの「縁日」に合わせて刊行している。
『悲嘆とケアの神話論―須佐之男と大国主』と『いのちの帰趨』は、わたしにとって、がんの宣告から手術をし、退院してしばらく(約40日後)までの間に書いた論考や詩篇を集めたもので、自分の意識の中では間違いなくステージⅣのがん患者の「遺言」で、この時にしか書けないものであったと思う。
とりわけ、『いのちの帰趨』は、入院中の阪神淡路大震災の起った1月17日午前5時46分から書き始めた詩篇20篇と、退院後の2月8日から3月21日までに書いた10篇の、合わせて30篇の詩を収めた実質的な「入退院詩集」である。
わたしは歌も詩も、考えることなく作るので、なぜそのようになったかは自分でもよく説明できないが、しかし、 『悲嘆とケアの神話論―須佐之男と大国主』がわが「金剛界曼荼羅」(智)だとすれば、 『いのちの帰趨』はわが「胎蔵界曼荼羅」(理と悲)である とその違いをはっきりと断言できる。 そして、この両書合わせて一つ(不二)であると。
これら、わが二種の「遺言」がどのように読まれるかは分からないが、しかしこの二著はどうしようもない「トラタヌ人生」の帰結で、成るべくして成った作物であるというほかない。
刊行に際し、本一般社団法人日本宗教信仰復興会議の出版助成を得られたことをここに明記し、心より感謝申し上げたい。
2023年8月23日記 鎌田東二
「信仰からの訴え」―その3(全4回) :水谷 周骨子
敗戦後もほぼ80年目を迎えようとしている。いわゆる「近代化」に精勤に励んだ結果が、今日の日本である。それは宗教的に誠に淋しい姿である。筆者は本年5月に『信仰は訴える』(国書刊行会)という一書を公刊した。その中で訴えたのは、4点あった。「信仰の訴え」の第三は、現代日本の宗教界には霊的なメッセージを発出することで、人々を導くという本来の責務を果たしてほしいという課題である。
地球の裏側の小さな事件でも、瞬時に世界を駆け巡る時代となった。他方、天災や人災は絶えることを知らない。人の心は、過剰な分量の情報に振り回される始末。喜怒哀楽の感情も揺り動かされ、「悲」の拡大が顕著になっていると言えよう。そこに人々の心が移ろい、空虚となり、迷いは救いを求めるという航路を辿ることとなる。つまり宗教の出番が増えているのが、今日の状況なのである。
この状況がもたらすのは、二つの現象であろう。一つは、明確な宗教意識に至る以前の、漠然とした信仰希求の気持ちであり、広義の宗教回帰の傾向である。二つには、宗教界としての細かな事案への対応が必要とされているという展開である。第一の無意識下の宗教性の側面は、夙に「スピリチュアリティの興隆」としてこの数十年間宗教学会で取りあげられてきて、今もその論議が継続されている。具体的には、東日本大震災を契機として2016年に日本臨床宗教師会が結成されるに至った。超宗教の立場から、悩める人々への救いの手をいかに差し伸べるか、真剣な議論と実践活動が進められている。
第二の宗教界の細かな出番の増加に関しては、「悲」の拡大に限らず、医療分野での患者の立場に立つ新たな取り組み、看取り術の広まり他、「癒し」の需要増加などの潮流も関係している。さらには、政治社会的な諸問題への参画も求められる。それは大きくは世界平和といった課題であるが、やはり人類社会の動向への責務として、宗教界の発言が目に付くのである。
さなきだに旧統一教会の日本国内における資金調達のすさまじさや、選挙活動などを利用しての政界への浸透振りが問題視されてきた。そして宗教が政治に関与してよいのかどうかといった観点も議論されている。現在の日本国憲法上は、宗教団体が政治に関与していけないという道理はない。それは経済団体や労働組合が、政治に訴えるのと同列だからである。しかし信者の心を把握して大衆動員が可能な宗教は、一端道を逸脱するととんでもない結果を全国民にもたらす事例をわれわれは多数見て来た。そこに宗教が政治介入するのは、無制限ではないとする論拠が見出せるのである。
それでは適切な政治関与とは何か。結論から言えば、例えば政治献金も一定の限度額を設ける、選挙活動への直接的参画は戒める、政党の結成は認められないといった諸例が挙げられるだろう。いまだ未整理の分野であるが、日本はすっかり戸惑いを隠せないでいるのである。
今ここで強調すべきは、宗教としての本務は何かということである。それは人々への霊的な指導である。つまり政治や社会の個々具体的な事案を直接取り上げるのではなく、それらの持つ精神的な意義を考慮し確かめつつ、霊的なレベルから発言し、指導し、あるべき姿を示すというのが、本務なのである。それを失念してはならない。
ウクライナの惨状を目にして、一斉に非難の声明が出されたのは、宗教団体も例外ではなかった。日本では20数本出された。その挙句は、どれを見ても異口同音の調子であり、ほとんど新聞も報道することがなかった。そこで最後の段階で、某宗派では、あまりに影響力を失っているので、これ以上同種の声明を出すのは控えるという趣旨の声明が出された。これは笑ってすむ話ではない。それほどに、どの声明も霊的なレベルの発想と発言がなされなかったという証左になるからである。
霊的レベルの声明であれば、たとえ似た言葉であってもそれぞれに吹き込まれた息吹が異なるので、どれをとっても新鮮さと迫力が維持されているはずである。このような精神界を導くとの強い意向は、定期的に出されているコーマ教皇のメッセージに好例を見出せる。その効果の理解には、手間取らないはずである。日本の宗教界も掛かる好例を参考に、日本国民を霊的に導かねばならない、それが固有の本務であるということを、今一度想起してもらいたいのである。
「信仰からの訴え」―その2(全4回) :水谷 周骨子
敗戦後もほぼ80年目を迎えようとしている。いわゆる「近代化」に精勤に励んだ結果が、今日の日本である。それは宗教的に誠に淋しい姿である。筆者は本年5月に『信仰は訴える』(国書刊行会)という一書を公刊した。その中で訴えたのは、4点あった。「信仰の訴え」の第二は、日本人の宗教アレルギーを克服するという問題である。
現代日本は宗教アレルギーに病んでいると言えよう。その原因は、戦前の国家神道支配の悪い経験と思いである。「神や仏は何もしてくれなかった」という実感が襲い、他方日々の生活もままならぬ経済復興の絶対命題が身に迫っていた。これに輪を掛けたのは、米軍他の連合軍司令部による徹底した政教分離政策であった。公教育から追放された宗教教育は、社会の片隅の存在となり、宗教離れが制約なしで進行してしまったのだ。
そこで信仰者は、心が弱いか病んでいる人と同列に置かれることとなった。本来は、宗教行為は神々しくも晴れやか面持ちで臨むものであるはずが、親にも言えず肩身の狭い行為という位置付けになった。
宗教がどれほど社会の片隅に置かれているかを、ここでいくつかの事例を挙げて見ておこう。特段の順序はない。
・自殺者の多いことでは、日本は先進諸国の中でもトップクラスである。
・いつも生きがいが話題となり、死の枕に着いても心は千々に乱れることが多い。
・宗教学校でも儀礼を拒否する親の多いこと。
・称賛されるべき事例(アフガニスタンで銃殺された中村医師など)に際しても宗教界からの称賛が聞かれないことに、不満の声が出されない。
・道徳観念の希薄化、弱体化については、漸く公教育で学科として復興された。
以上のような状況は、実は世界のどこでも見られるものではなく、日本はよほど特殊な事情に陥っていることを確認したいのである。現状の宗教離れは、一つの病気として治癒されなければならないが、それが第二の訴えである。
日本人は無宗教であるとされる一方、神社仏閣への参拝は盛んである。墓参も絶えることはない。だから宗教熱は絶えて居ないことは確かだが、多くの人は、参拝は宗教であるとの自覚を持っていない、つまりそれは社会の習慣として気持ちの上で位置付けているからだとされる。確かに明確な宗教意識ではないにしても、淡いながらそれらに宗教意識がまといついていることも否定できない。それは人として、結局宗教を消去することはできないという、自然なこころの傾きの表れであるからだ。
要は日本はどのように宗教に向き合うべきか、戸惑い当惑しているのが現状である。その間、オーム真理教や旧統一教会などのかたよった現象ばかりが目立つ結果となってきた。これも不幸に輪を掛けている。人間本来の精神的安寧を求める気持ちを正面から認めて、それと素直に向き合える状況と環境を求めるということになる。
これを実現するのは、実はほとんど歴史を逆転させるほどのエネルギーと相当な時間が必要となる。しかしそれに着手するか否かに、今後の日本の命運がかかっていると思料されるのである。そのための、日常的な単純な課題も含めて、以下のような諸措置が提唱できる。
・祈りという所作を日常生活に取り込むこと。作法や祈りの内容は個人個人で全く自由なものとする。現世を離れた事柄に頭を巡らせることで、思考を活性化できる。一年に一日は、自分の「祈りの日」を設定することも一案。
・近くの神社仏閣など宗教施設を厳かな心持で訪れること。付き合いや習性としてではなく、自発的な行為としての意識を持つ。
・宗教書を手に取ってみること。いずこの図書館にも、実は宗教書の類は棚に溢れんばかりである。読書グループもあるので、宗教書を取り上げることを提案してみること。
・宗教に関心を持つ人たちと、交流し、友好関係を維持すること。仲間が増えれば楽しくなるのは、人の常。
・宗教をもっと普通の会話の話題とできないだろうか。
・数少ないが、宗教をテーマとするテレビ番組をできるだけ視聴する。例えば、NHKの「こころの時代~宗教と人生~」は、毎週日曜日午前5時とその再放送が土曜日午後1時から放映されている。よく練られた内容が大半であり、見ごたえがある。
・最終的には、公教育において宗教に関する内容を取り込むこと。それは特定の布教目的であることは排除されるが、世界における宗教の役割や世界の大半の人々は信奉しているという事実、そして宗教を信じている人々への敬意を学ぶことなどがある。日本固有の宗教の伝統とその価値への理解促進も必要であろう。
書評原稿「石川啄木/宮沢賢治/ヘルダーリン」2023年6月8日記 :鎌田東二骨子
先だって、2023年6月4日(日)に、「第90回身心変容技法研究会」を開催し、詩人であり、石川啄木の研究者であるの明治大学教授の池田功さんに、石川啄木論を100分かけて詳細に発表していただいた。そして、鶴岡賀雄さん(東京大学名誉教授・宗教学・スペース主義研究)、津城寛文さん(筑波大学名誉教授・宗教学・神秘宗教/公共宗教研究・歌人)、やまだようこさん(京都大学名誉教授・発達心理学・ナラティブ心理学)と、次回(2023年8月5日(土)13時‐17時開催:http://waza-sophia.la.coocan.jp/ 参照)第91回身心変容技法研究会に発表者となってもらう鈴木寅二啓之さん(羽衣国際大学非常勤講師・土中神社創作・顔画研究創作)にコメントしてもらった。それぞれにヒント満載であった。
私はほぼすべての著作で言及しているように宮沢賢治ファンである。その宮沢賢治(1896‐1933)には妹宮沢とし子や親友だった保坂嘉内に対する過剰なセンチメントがあると思ってはいるが、石川啄木(1886‐1914)にも極めて過剰なセンチメントがあると感じる。だが、後者のセンチメントに対する感傷的な共感はあまりない。
スペイン神秘主義の研究者の鶴岡賀雄さんは、しかし、その石川啄木の「詩心」や「詩魂」を、「中学生みたいな心情・純情」とコメントしてくれた。実に言い得て妙で、まさに石川啄木は「盛岡中学校」の生徒で(実際は5年生の1学期でカンニングがきっかけで中退らしい)で、中学生をそのまま生きぬいた若者だった。
それが、私が強い関心を持つ、1910年=明治43年8月に書いた「時代閉塞の現状―強権、純粋自然主義の最期および明日の考察」を生み出したのだ。この論考は、あまりに純情率直(直球ど真ん中、ストレート)で、朝日新聞も彼が関わってきた新聞雑誌もみな、大逆事件(1910年5月に勃発)後のメディア圧力をびびっていたのだ。
この論文は、最初、朝日新聞に発表するために書いたとされる。日本帝国の「強権」や時代の流行である「純粋自然主義の『最後』」について赤裸々に語り、そして「明日の考察」の希望を語った。この論文は、同じ年に発表された魚住折蘆の「自己主張の思想としての自然主義」に対する反論として書かれたと池田功さんは指摘してくれた。だが、この熱の籠った論考は、啄木の生前には発表されず、土岐善麿の支援を受けて『啄木遺稿』と題して1913年(大正2年)に東雲堂書店から出版されたのである。
魚住折蘆の論考に触発されながら、魚住説を批判的に吟味し、この時代状況の「時代閉塞」を広く現状認識しつつ批判的に吟味し突破口を切り拓こうとしたこの論文を私は高く評価する。時代状況を見据えながら、中学生詩人の魂は震える「叫び声」を挙げて、この時代に警鐘を鳴らしているのだ。その切迫感が痛いほど伝わってくる。こんな「詩魂(士魂?)」を生涯持っていたいものだ。
しかし、残念ながら、その声はその時代にすぐに、ストレートには届かなかった。だが、100年余後の私たちにはしっかりと届いている。
とはいえ、ちょっと皮肉で笑いたくなるような余談であるが、どうやら岩手県内には「石川啄木派」と「宮沢賢治派」の「二大派閥」があるようだ。そして、両者はしのぎを削り、機会あるごとに闘い合っているとのことを聞いた。その気持ちも分からないではないが、それよりも、同じように生前不遇であった夭折詩人として、地元においてはなおのこと、「相克」ではなく「相生」の方向で、より広く深く日本および世界の「詩心」と「詩魂」を甦らせてもらいたい。
私にとって、「宗教信仰復興」とは、まず「神話復興」であり、同時に「神話詩復興」である。私はそれを、新刊『悲嘆とケアの神話論ー須佐之男・大国主』(春秋社、2023年5月3日)と、来月出す第7詩集『いのちの帰趨』(港の人、2023年7月22日刊)で「遺言」として示し問題提起したつもりである。
その過程で、本年2月末の「第5回いのちの研究会」以降、加藤敏さんとの交流を通してヘルダーリンの詩に強い関心を抱くようになった。1970年代に邦訳の『ハイデガー全集』を読み、その中にあった『ヘルダーリンの詩の解明』も読んではいた。しかし本当にはよく分かっていなかったのだ。
そこで『ヘルダーリン全集』(河出書房新社)を2種類も買い揃え、文庫本の詩集も全部買って読んだ。そしえ、読めば読むほど、静かに、深く、へんな喩えだが、奈落の底に墜ちていくかのように共感した次第であった。そのことを、来月出版する第7詩集『いのちの帰趨』(港の人)の「あとがき」に次のように書いた。
<最近、ヘルダーリンの詩を読んでいて気づいたことがある。それはヘルダーリンが1770年年3月20日生まれであることだった。「はるのことわけ」に書いたように、梅原猛さんも後藤人基君もわたしも同じ日に生れた。それにより、なぜか一挙にヘルダーリンの詩がよくわかるようになってきた。
特に、『ヒュペーリオン』など、自分で書いたものであるかのような錯覚に陥った。不審に思われるなら、また不遜だと思われるなら、ヘルダーリンの『ヒュペーリオン―希臘の世捨人』(渡辺格司訳、岩波文庫、1936年)とか『ヘルダーリン詩集』(小牧建夫・吹田順助、1959年)と拙著『悲嘆とケアの神話論』(春秋社)の「神話詩」を読み比べていただきたい。わたしはヘルダーリンの「詩人」観や「詩心」や「詩想」との共通性にしんそこおどろいていたのだ。
ヘルダーリンは、次のような「詩人」観を表明している。
だが,われらに相応しいのは,おお詩人たちよ 神の雷雨のただ中に頭を曝して立ち 父の光を,そのものを手ずから 掴み,そして歌にくるんで 民に天の賜物を頒つことである (「あたかも祝いの日のあけゆくとき」手塚富雄訳、『ヘルダーリン全集第2巻』河出書房、1974年)
これを読んだとき、慄然とした。
「神の雷雨のただ中に頭を曝して立ち/父の光を,そのものを手ずから/掴み,そして歌にくるんで/民に天の賜物を頒つ」という感覚に何とも言えぬ共感を通り越した「狂(喜)感」を抱いたからだ。ここに自分と同類の「詩人」がいる、というような感じ。この中で異なるのは、「父の光」というところだけである。わたしの場合、それは「大妣の光」であり「自然の光」であって、「父」と特定できるものではない。
しかしながら、「神の雷雨のただ中に頭を曝して立ち」というのは、17歳で青島を訪れ、その衝撃で火山弾を吐き出すように詩を書き始めた自分の感覚を絶妙の表現で言い表わしてくれていた。うれしかった。これを読んで。自分は一人(独り)ではない、としんそこ思った。それを読んで感動していたときには、ヘルダーリンが3月20日生れであることは知らなかったが、誕生日が同日であることを知ってさらに納得がいった。
自治医科大学名誉教授の精神科医の加藤敏さんは「狂気内包性精神病理学」(『精神医学史研究』Vol.24、2020年6月発行)と題する論文の中で、ヘルダーリンの上記の詩に対して、
<この詩で述べられる「神の雷雨」にさらされるという事態は,強度の高い存在が立ち現れて詩人に押し付けられ,詩人がこれに所有されるということを指し示す.詩人にとってこの強度の高い存在の圧倒は不安や恐怖のなか彼を魅惑し,享楽をもたらす.『存在と時間』以後,ハイデガーのひとつの鍵言葉となる「聖なるもの」は,「恐るべきもの」であるという様相をもって立ち現れる強度の高い存在を指し示す./精神医学の見地からすれば,こうした在り方は,統合失調症急性期の世界変容に通じる.ヘルダーリンは月並みな患者とは異なり,急性期の体験のなかにあって,これから逃げようとせず,逆にそこに敢えて踏みとどまろうと務め,強度の高い存在の突出を言葉によって首尾よく捕りおさえる.これがヘルダーリンの詩作にほかならない.>(83頁)
という解釈を与えている。
わたしも自分が統合失調症的な人間であることは重々自覚してきたので、このことは身をつまされる感覚でよくわかる。しかし、わたしには神仏というか何か超越的な力でマンダラ的に「統合」されるものがあるために、統合失調症であるわけではない。にもかかわらず、統合失調症の症例分析などを読むと、自分のことのようによくわかるのだ。
加藤敏さんによると、ハイデガーはヘルダーリン論の中で、「詩人とは外に投げ出されたもの」、「即ち,神々と人間の中間の投げ出されたものである」(『形而上学とは何か』大江清志郎訳、理想社、1969年)とか、「根源の近くへと来る」(「ヘルダーリンの詩の解明」手塚富雄・齋藤信治・土田貞夫・竹内豊治訳『ハイデガー選集』3、 理想社、1955年)とかと述べていると指摘している。これまた「吟遊詩人」を自称するようになったわたしにはよくわかる。
そんなこんなで、「あとがき」が異様に長くなって申し訳ないが、この詩集をまとめながら、17歳から「吟遊詩人的ガン遊詩人」の今までの自分自身の歩みの本質というか本性がよく見えてきたような気がする。>
要するに、ヘルダーリンの「頭」が「神の雷雨」に晒されて、雷光と雷雨のシャワーを浴びて、「頭」と身心魂がグルグルになっていたということこそが重要なのだ。他のなによりも。
そのことを、「詩人は聖なる夜に国から国へさすらいゆくバッカスの聖なる司祭の如きもの」と言っている。詩人はバッカスすなわちディオニュソスを祭り、その神の「雷雨」を全身で浴びる旅する人(能で言うところの「諸国一見の僧」)である。その旅人が見、聴きする光景と声を届けねばならぬ。そのような使命を果たさねばならぬ。「詩人」はそうしたミッションを持って流離い往くのだ。
当年75歳で畏敬する精神科医の加藤敏さんに、ヘルダーリンの当該詩には何種類(少なくともわたしが読む限り3種類)かの訳文があり、その中で加藤敏さんが引用している我が「あとがき」に引用した訳文が一番身心魂に響いたので『ヘルダーリン全集』を買って読んだけれどもその訳文とは異なるので、引用訳文を確かめてその頁をPDFで送ってほしいとお願いしたのである。たいへんありがたいことに、加藤敏さんは極めて多忙な中、自治医科大学所蔵の上記書物で確かめてくれた。そして、改めて、加藤敏さん同様、加藤さんが引用した土田貞夫・竹内豊雄訳がもっともよい訳だと思ったのだった。
しかしながら、当然のことだが、訳文によってかなりニュアンスやインパクトが異なるのだ。そのことは、詩を書く人間として重々分かっていたことではあったが、しかし、<詩の鑑賞>としては問題含みである。やはり、ヘルダーリンのドイツ語原詩を熟読玩味することなしにヘルダーリン理解をしたとは言えない。もちろん、そのことなしには、ヘルダーリンのテュービンゲン大学神学校時代の寮の同室者でヘルダーリンの詩に多大な影響を受けたと言われるシェリングはヘーゲルの理解もハイデガーの理解も十分にはできないことは明白である。そこで、明日(6月9日)に京都大学総合図書館に行ってドイツ語の『ヘルダーリン全集』を借り出して読んでみることにする。
50年以上も昔のこと、ヤコブ・ベーメと空海の神秘体験と言語哲学を比較研究するスト業論文を書いた哲学科の学生であった頃から、修士論文で「宗教言語の研究」を書いて、その後『記号と言霊』(青弓社、1990年)や『言霊の思想』(青土社、2017年、1999年に筑波大学に提出した学位請求論文・博士論文)をまとめたが、20代前半にはけっこうドイツ語は読む努力をした。そして、第一外国語の英語もいろんな人から、第二外国語のドイツ語は中野孝次さんから、第三外国語のギリシャ語と第四外国語のラテン語は東千尋さんから、第五外国語のサンスクリットは松涛誠達さんから、第六外国語のフランス語は竹内芳郎さんからと、錚々たる先生たちに習って、それらをかじりはしたけれども、到底ものになっていない。そこで、一大決心をし、本年72歳を再スタート時として、まずはヘルダーリンの原詩のドイツ語から熟読吟味鑑賞することにして、いずれは、何年か後には、わが「青春の門」の聖書であったロートレアモン伯爵(イジドール・デュカス)の『マルドロールの歌』をフランス語で読みたいと思っている。
そのような、本年8月18日(金)から「詩を原詩で読む会(講? 結?)」をオンラインで作る予定である。
*本エッセイは「書評」と言えるものではないが、「書籍紹介」欄にはいくらかふさわしいコラム記事かもしれない。何冊かの本の紹介もしているので、本コラムを「書籍紹介」欄に投稿した。 2023年6月8日記
「信仰からの訴え」―その1(全4回) :水谷 周
骨子
敗戦後もほぼ80年目を迎えようとしている。いわゆる「近代化」に精勤に励んだ結果が、今日の日本である。それは宗教的に誠に淋しい姿である。筆者は本年5月に『信仰は訴える』(国書刊行会)という一書を公刊した。その中で訴えたのは、4点あった。信仰の訴えの第一は、信仰を探訪する信仰学が欲しいということである。
客観性順守の立場から、信仰を学問することはないとされてきた。美術を研究するのに美学や美術史があり、音楽も音楽理論がある。研究者が特定の信仰を持つことが、すなわち中立性を失うとすれば、政治や経済他社会科学の分野も同様に難しいということになる。 究極的に何を信条とするかという問題と、それとはひとまず距離を置いて広く情報収集をして、総合的に検討し分析するという課題とが混同されているのではないか。そして最終的には、絶対的な客観性はそもそも存在せず、主客のせめぎ合いというのが、人間の認識能力の限界ということは、広く認められてきている。自然科学でさえ、事物は人力で実証可能であり、それは客観的であるという前提・信念が出発点であるが、その前提を揺るがせにする不確定な現象も提示されつつある(カオス理論など一連の曖昧科学として整理され、それは未だにある種疎外されている)。 要するに、信仰学という分野を開拓すべきではないか、というのが「信仰の第一の訴え」である。信仰は宗教の核心である以上、それを埒外の別問題だと決めつける立場は、結局信仰はおろか、宗教そのものの真髄であり最強の部分を遠ざけているのではないだろうか。 すでに他界されたが、日本の宗教学の大御所は、次のように語っていたという。 宗教学者は宗教をもってはならない。入信することにより、自分の宗教という 色眼鏡を通して他の宗教を見ることになるからである。そのため、宗教学のもつべき学としての真理の把握に不可欠な客観性が損なわれる。しかし、他方では、信仰をもたなければ、その宗教の秘奥はつかめない。これが宗教学者のディレンマである。 しかしこの碩学も、死に直面しては、相当な心境の変化を見せたのであった。 死とは、この世に別れを告げるとき考える場合には、もちろん、この世は存 在する。すでに別れを告げた自分が、宇宙の霊にかえって、永遠の休息に入るだけである。私にとっては、すくなくとも、この考え方が、死に対する大きな転機になっている(奥村一郎「死と祈り」、『岩波講座 宗教と科学』第7巻、331―362頁所収)。 ここにおいては、「宇宙の霊」であるとか、「永遠の休息に入る」といった、優れて宗教的な発想を取っている。近く迫る死がかの大学者の気持ちの持ち方にも、不思議な転換をもたらしたと言えよう。 それでは信仰学はどのように開拓されうるのだろうか。それはあまり肩に力を入れる話ではないと思われる。まずは既存の信仰に関する文献や言動、そして事跡を広く収集整理することで、直ちに着手できる。そういったアプローチはいわばアナログの手法であるが、先々は脳科学など認知諸科学との連携も当然必要になる。だからと言ってそれで人が求める信仰を代行するサイボーグの登場までは、予測あるいは期待するものではない。相当信仰の終極に迫ることになるとしても、どこまで行っても機械は機械である。 改めて、なぜ信仰学が希求されるかを確かめておきたい。それはほとんど、宗教を希求する心、つまり求道の精神と同義である。宗教が論じられる中で、信仰だけは枠外とするのは、的はずれになるということだ。信仰を持つ立場の人たちを、心理的に差別する結果も招来していると思われる。心の弱い人とか病んでいる人が信仰しているといった一般通念の原因となっているのではないか。宗教に帰依することは、本来神々しくも晴れやかなものなのである。このギャップは次回の論点である、「現代日本の宗教アレルギー」とつながってくるポイントである。 信仰を希求するのは、人間として自然であり、そのような精神的な安寧を獲得することは、全幅の人間性の実現の一端である。それは敗戦後の日本社会を背景とする場合は、人間復興と呼べるだろう。アレルギー症状を克服することで、全き人の姿が顕現する。そうでない現在の日本は、世界的にも特殊な状態に置かれているという歴史認識も求められていることになる。
弱さの強度~佐藤泰志『そこのみにて光輝く』(河出文庫)との出逢い :鎌田東二
要旨
比叡山に登拝しながら考えた(東山修験道811 )、「弱さの強度」について。弱いのに強い(勁い)というのは矛盾しているようであるが、そうでもない。
たとえば、『古事記』に描かれる大国主神などは、その典型に見えるから。何しろ、兄神たちの徹底的ないじめを受けて、いつも荷物持ちとか、下働きとかをさせられていた。 しかし、大国主神は心優しく、兄神たちに騙されて傷ついていた稲羽の白兎を助けた。適切な医療的処方箋を示して。その大国主の心に反応してか、白兎は稲羽の八上比売を得ることができるのは兄神たちではなく大国主神だと予言し、その通りになった。 だが、兄神たちの嫉妬をかって、大国主は二度も兄神たちに殺された。けれども、母や祖神(神産巣日神)の力で甦ったのだった。二度とも。そして、母神たちのサゼスチョンで、父祖神のスサノヲの住む根の堅州国に行き、スサノヲの娘の須勢理毘売の助けで厳しい課題を切り抜け、その後は少名毘古那神の助力を得て国作りをすることができた。 しかしながら、せっかく少名毘古那神とともに一所懸命に作った「国」を天孫に「国譲り」したのだった。だが、その見返りとして「天の御舎」(杵築大社・出雲大社)を得ることになった。 私はこの大国主神の弱さの奥にある予測しがたい粘り強い勁さを、「最弱の神が最強の神となる反対の一致」の物語として、第四詩集『絶体絶命』(土曜美術社出版販売、2022年5月30日刊)で描いたのだった。その反転(逆転)する神の軌跡がこの春から私の心に棲みついて離れず、本年末の12月には35年も研究発表していなかった神道宗教学会で、「痛みとケアの神としての大国主神」と題して発表することにしたのだった。 これは、私の中ではちょっとばかり、革命的な変化である。 ところで、この9月に、「吟終詩人」として北海道を巡遊した。9月17日に旭川、18日に札幌、19日に函館で、『絶体絶命』の詩の朗読と「神道ソング」を数曲歌った。それは私にとってかなりな「革命的な変化」だったが、旭川で三浦綾子と小熊秀雄という二人の問題提起的な文学者(一人は小説家、もう一人は詩人)に出会ったことは、すでにエッセイにしたためた。 この二人とも「弱さの中の強さ」を問いかける文学者でもあると思っているが、じつは、もう1つ、大きな出会いがあったのだった。函館で、佐藤泰志という小説家と会ったのだった。だが、彼はすでに死んでいた。 1949年に函館に生まれた佐藤泰志は、何度も芥川賞や三島由紀夫賞の候補になりながら受賞には至らず、1990年10月、首を吊って自死した。1989年には『そこのみにて光輝く』で三島賞候補となったが、その年の受賞者は大岡玲の『黄昏のストーム・シーディング』だった。 私が函館で詩を朗読し歌を歌った、津軽海峡を望むことのできる「サン・リフレ函館(函館市勤労者総合福祉センター、愛称サン・リフレ函館)」は、佐藤泰志が通っていた旭中学校の跡地に建設された市の施設なのだった。その2階の音楽室で、私は佐藤泰志のことなどまったく知らずに(その時はそう思っていた)「神ながらたまちはへませ」とか「なんまいだー節」など数曲を歌ったのだった。 佐藤泰志の名を知ったのは、朗読会終了後、主催者の番場早苗さんや何人かの函館の詩人たちと懇談をしていた時だった。「函館の佐藤泰志が……」などという詩人の番場早苗さんの言葉が耳に残っていたのか、その夜、宿泊しているホテルの売店で佐藤泰志の小説が置いてあったので、それを買い求めて読み始めて驚いたのだった。 函館で買った佐藤泰志の小説『そこのみにて光輝く』(河出文庫、2011年)は、熊野・新宮を舞台に描いた中上健次の小説をちょっと函館にスライドさせたような小説だと思ったが、作者が國學院大學文学部哲学科の出身であることがプロフィール欄に書いてあるので、ハッとした。 そして、思い出した。顔写真を見てどこか知っているような気がしたのは、哲学科の何かの授業で彼と会っていたからだった。東教授か中川教授かいずれかの授業だったと思うが、議論の最中、わたしは「キミの言ってることは当たり前すぎてつまらないよ。」というようなことを言ったように記憶する。その時、彼はさみしそうな顔をして、それ以上の反論をしなかった。そんな映像が脳裏に残っている。 この記憶が正しいかどうか、今となっては確かめるすべはない。その場にいた学友たちの名前も顔もすべて忘れているからだ。だが、彼の顔だけはよく覚えている。それを函館のホテルで買った文庫本の帯の顔写真からフラッシュバックのように思い出したのだった。 小説の内容については、本エッセイではあえて触れないでおく。厳しい言い方だが、私にとっては目新しいものではなく、中上健次(1946‐1992)の影響を受けた亜流文学のように思えた。中上健次という強烈な作家と対談したこともあるのでしようがないとも思った(中上健次・鎌田東二対談集『言靈の天地』主婦の友社、1994年)。 だが、読後に、中上健次の壮絶な癌死(腎臓癌)と佐藤泰志の自死に、何か共通するものを感じたのだった。それは、理不尽な暴力というか、攻撃的なものに対して、どうしようもなく巻き込まれながらも、そこで生きていく人間の悲しみ、悲哀のようなものである。 私たちの世界はさまざまな暴力に晒されている。その暴力を回避することはできない。その押し寄せる暴力の波の中で、どのような生存を全うできるのか? 中上健次は浴びるように酒を飲んで死んだ(私との3日間の対談の始めから終わりまで彼も私も酒を飲み続けていた)。そして、佐藤泰志は……。 佐藤泰志の自死の理由は分からない。文学的な行き詰まりがあったのかもしれない。あるいは、受賞を逃したことを含め、はかばかしくない社会の反応に絶望する思いがあったのかもしれない。それは分からないが、しかし、佐藤泰志の悲し気な顔、「おまえはわからないんだな。わかってくれないんだな。」とでも言いたげな、その悲し気な顔がずっと気になり尾を引いている。言葉ではなく、ノンバーバルなその表情が言葉以上のナラティブを語っているような気がする。だが、そのナラティブを明確に読み解くことが私にはできない。 津軽海峡と太平洋の海の見えるグランドピアノの置いてある音楽室で私は石笛・横笛・法螺貝を奉奏し、ギターを抱えて海を見ながら歌を歌った。 後から考えると、それは佐藤泰志への私からの鎮魂歌のように思ったのだった。独りよがりな思いだと言われるかもしれないが、死後の佐藤泰志と私は出逢い直し、対話し直し始めているような気がしている。 佐藤が書いた哲学科の卒業論文の題目は「神なきあとの人間の問題」だったという(※)。ちなみに、私の卒業論文の題目は、「東洋と西洋における神秘主義の基礎的問題への試論」という長たらしいもので、主として、空海とドイツの神秘哲学者のヤコブ・ベーメの神秘体験と言語哲学との関係を問いかける内容だった。つまり、「神仏を体験した人間の問題」で、佐藤泰志とは対極にある問題の探究だった。今となっては、佐藤ともっと話がしてみたかったと思わずにはいられない。『そこのみにて光輝く』という表題に佐藤泰志が込めた思いは何だったのだろうか? 脚注 ※
函館市文化・スポーツ振興団HP なお、没後30年を迎えた2010年、佐藤泰志の短編小説集『海炭市叙景』が熊切和嘉監督により映画化された。その後続けて、『そこのみにて光輝く』が2014年に呉美保監督により、『オーバー・フェンス』が2016年に山下敦弘監督により映画化され、「函館3部作」とされている。映画『そこのみにて光輝く』は、主人公役を綾野剛、その義弟役を菅田将暉が演じ、第38回モントリオール世界映画祭最優秀監督賞、キネマ旬報ベストテン1位を受賞している。ヒロインを演じた池脇千鶴は、同年の日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞している。
旭川で出会った小熊秀雄(1901‐1940)と三浦綾子(1922‐1999) :鎌田東二
要旨
「吟遊詩人」として北海道を旅した。9月16日に羽田空港を経由して旭川空港に降り立つと、詩誌『フラジャイル』主宰者の旭川の詩人柴田望さんが迎えに来てくれていた。
前者のことは、テレビドラマ化された「氷点」で知っていたが、作品そのものは読んだことがなかった。また、キリスト者であることも知っていたが、それが彼女の文学活動や作品とどのようにつながっているのか、関心はあったもののよく知らなかった。 それが今回の三浦綾子記念文学館の見学で大転換した。三浦綾子が文学者として、また信仰者として、生涯のテーマとしたのが、「罪」と「悪」と救いだということを知ったからである。これは、本格的に三浦綾子全集を読んでみなければならないと強く思うに至った。 わたしはこれまで、遠藤周作の大ファンであることを公言してきたが、それは遠藤が人間の弱さとそれゆえに犯す犯罪と悪に関心を引かれてきたからである。三浦綾子は遠藤よりも1歳年上で、遠藤より3年長生きしている。ほぼ同時代を生きた。 満州の大連育ちの遠藤周作と北海道の旭川育ちの三浦綾子が、二人とも「日本」という国に違和の念を抱きながら育ったであろうこと、そして、それが彼らの文学創作に深いところから影響を与えただろうこと、そのことを考えてみたいと思うに至った。 来年、また北海道を訪ねるつもりであるが、その前にあらかた三浦綾子の主作品は読んでおきたいと思う。そして、柴田望さんを始め、地元の詩人の方々と三浦綾子論を対話してみたい。 今回、わたしがもっとも衝撃を受けたのは、小熊秀雄という詩人の存在であった。小樽で私生児として生まれ育ち、旭川で新聞記者(旭川新聞)となって活動を始めた小熊秀雄の詩人としての多彩で多作で豊穣で爆発しているその作品群に、衝撃とともに、強い関心を抱いた。 この詩人の「闇」の深さと「批評」の鋭さ。これもまた生ぬるい「日本」に生きている者からは生まれてこないロンギヌスの槍のような射力がある。彼の日本の小説家や詩人たちに加えた辛辣に射抜いた批評詩は日本の「文壇」には完全に異質でありながら、見事な批評性とエスプリとブラックユーモアを称えていて、文学的達成としても見事であり、優れている。 この知性と批評性がどこから生まれたのか? そして、その「心の闇」の深さも含めて、再度か再再度か現代に蘇る詩人であることは間違いないと思うのだ。(2022年10月1日記)
詩人と秘密 秘密は沢山だ、散文家にまかせてをけ 彼等が秘密を保つこと大きければ 大きいほど大きな仕事ができるから――。 私は詩人だ秘密は大嫌ひ 現実から秘密を発見し それを披露して人々に嫌な顔をさせたい だが、すべての詩人は嘘吐きめだ、 まだまだ秘密の公開が足りない 君は真実の歌をさらけ出さない 散文家の大きな嘘は認めてやらう 小さな嘘は笑つてやらう 詩人の嘘は大小に拘はらず認められない 私は小さな嘘吐き共とたゝかふために 生活の上でも、 思想の上でもこんなに苦しんでゐる 馬鹿々々しいスタイリスト詩人共 日本にこれまでよき詩がないのは 君等が嘘でかためたニカワのやうに 立派に観念を固めるからだ 私のふるへる心臓をどうするのだ どうしてこれを他人が押へようとするのか、 いまこそ知らせてやれ いかに詩人とは生活が滑稽で 語ることがをかしくて 道化者のやうであるかを知らしてやれ さて詩人の生活をものの二時間も語つてやれ 最初は面白がつて聞いてゐた奴等も しだいに憂鬱な顔になるだらうから 秘密をさらけ出す詩人の性情は すべてに憎まれるか迷惑がられる それを怖れるな 大きな秘密を発見して それを大きな考への下に披露してしまへ。 (「新版・小熊秀雄全集第4巻」創樹社、1991年)
文壇諷刺詩篇 序 僕が小説家に対して、反感を抱いてゐることは確かだ、人に依つては、それが不思議なわけのわからぬことに思はれるだらう、一口で言へば「どの小説家もみんな良い人」なのだから、しかし僕はこの反感的な形式である諷刺詩を自分のものとしてゐるのは、それは抜差しのできない僕の生活の方法だから仕方がない。詩を攻勢的な武器として成立させてをかなければならないといふ社会的慾望から出たものだ。そして散文に対する反感は、僕といふ詩人と小説家との「時間に対する考へ方」の喰ひちがひから出発したものだ、この詩は昭和十一年から十二年にかけて読売新聞に発表したもの、諷刺雑誌「太鼓」に発表したもの並に未発表のものを加へて数十篇のうちから選んだ、自分ではこれらの詩を収録記念することを無価値なものとは思つてゐない。
志賀直哉へ 志賀の旦那は 構へ多くして 作品が少ねいや 暇と時間に不自由なく ながい間考へてゐて ポツリと 気の利いたことを言はれたんぢや 旦那にや かなひませんや こちとらは べらぼうめ 口を開けて待つてゐる 短気なお客に 温たけいところを 出すのが店の方針でさあ、 巷(ちまた)に立ちや 少しは気がせかあね たまにや出来の悪いのも あらあね、 旦那に喰はしていものは オケラの三杯酢に、 もつそう飯 ヘヱ、 お待遠さま、 志賀直哉様への 諷刺詩、 一丁、 あがつたよ。
佐藤春夫へ 男ありて 毎日、毎日 牛肉をくらひて 時にひとり さんまを喰ひてもの思ふ われら貧しきものは 時にさんまを喰ふのではない 毎日、毎日、さんまを喰らひて 毎日、毎日、コロッケを喰つてゐる 春夫よ、 あしたに太陽を迎へて 癇癪をおこし 夕に月を迎へて 癇癪をしづめる 古い正義と 古い良心との孤独地獄 あなたはアマリリスの花のごとく 孤高な一輪 新しい時代の 新しい正義と良心は 君のやうな孤独を経験しない 春夫よ 新しい世紀の さんまは甘いか酸つぱいか 感想を述べろ。
島崎藤村へ こゝな口幅つたい弱輩愚考仕るには 先生には――夜明け前から 書斎にひとり起きいでて 火鉢の残火掻きたて 頬ふくらませ吹いてゐる 嗜好もなく望みもなく たゞ先生の蟄居は 歴史の記録係りとして偉大であつた 先生はすぎさつた時に 鞭うつリアリストであり 新しい時をつくる予言者ではない こゝな口幅つたい弱輩愚考仕るには 先生には訪問者を 玄関先まで送り出し ペタリ坐つて三つ指ついて 面喰はせる態の 怖ろしく読者を恐縮させる 『慇懃文学』の一種である。
室生犀星へ 現実に これほど 難癖をつけて これほど 文句をつけ これほど しなだれかゝつて これほど次々と作品を 口説き落せば達者なものだ、 あなたは 果して神か女か、 神であれば 荒びて疲れた神であり 女であれば 暗夜、頭に蝋燭をともして 釘をうつ魔女だ しかし藁人形は悲鳴をあげない 呪はれる相手も居まい、 小説に苦しむたびに 幾度、 庭を築いては崩し 幾度、 石を買つては 売り飛ばし 老後の庭園を 掘つくりかへして 楽しんでゐるのは 御意の儘だ それは貴方の庭だから。 (「新版・小熊秀雄全集第3巻」創樹社、1991年)
宗教信仰を感得する本(仏教3冊、イスラーム2冊、キリスト教3冊)キリスト教③ :水谷周
要旨
宗教を紹介する書物は、図書館にも本屋にもネットにも溢れるほど見いだせる。そこでここでは、よく見る教科書的な紹介を繰り返すのではなく、筆者個人の目から見てその真髄を会得できるのではないかと思っているものを、多少選んで提供しようという趣旨である。それらが最善という意味ではないし、それ以外には見当たらないという訳でないことも自明の原理である。しかし個人的に心に響いたことなども含めて語ることで、読む人へも勘所が通じるのではないかという期待を込めて記すこととしたい。宗教信仰に関しては、直感が十分に働かないとどうしようもない面が強いので、このような経験的なアプローチを試みることとした。
3.『隠者の夕暮れ』 (ヨハン・ハインリッヒ・ペスタロッチー『隠者の夕暮れ』岩波文庫、一九四三年。) スイスで貧民教育に力を注いで知られたペスタロッチー(一七四六年―一八七七年)の随筆には、彼のキリスト教信仰への情熱がほとばしっている。 「七七 神に対する信仰は人間の本性の最も高い関係における人間感情の情調であり、神の親心に対する人類の信頼する子心である。 八〇 神に対する信仰よ、汝は人類の本質のうちに秘められている。善と悪とに対する感覚と同様に、正と不正とに対する打ち消しがたい感情と同様に、汝は人間陶冶の基礎として、われわれの本性の内部に揺るぎなく確固として横たわっている。 八二 神に対する信仰よ、汝は陶冶された知恵の結果や結論ではない。汝は単純性の純粋な感じであり、神―父まします―という自然の呼び声に耳傾ける無邪気な耳である。 八九 単純と無邪気、感謝と愛とに対する純粋な人間的な感情が、信仰の源泉である。 九〇 永遠の生命の希望は、人類の純粋な子心の中に湧いてくる。しかも神に対する人類の純粋な信仰は、こうした希望がなくては、彼の力の中に生きてはいない。 九八 人間よ、汝の本性の奥底に、真理と無邪気をそして単純とを、信仰と崇敬として聞くものが横たわっている。 一〇九 崇高な自然よ、このようにして汝は、汝の陶冶のうちに私の義務と私の悦楽とを結びつけ、また汝に導かれて人間は味得された浄福より新たな義務へと巡礼する。 一二三 神の信仰よ、汝こそこの希望の力である。 一二八 不信仰は人類の同胞としての地位と同胞としての義務との否認であり、神の父としての権利の誤認と蔑視とであり、対立する暴力の濫用における傲慢な大胆さであり、人類の浄福関係の全ての純粋な紐帯の解離である。 一三五 国民精神における正義と無邪気とに反抗する暴虐と厚顔無恥な僭越心とは、すべての国民衰微の源泉である。だから不信仰が、この衰微の源泉である。 一四〇 罪に対する嫌悪は、神に対する人類の子心の純粋な感情であり、人類の本性の内部における神の啓示に対する人類の信仰の表現でもあれば、またその結果でもある。 一四四 不信仰は、社会のすべての内面的な紐帯を断つ源泉である。 一六一 一切の不信仰は不遜であるが、しかし神に対する信仰、神性に対する人類の子心は、人類活動のいかなる力にも静かな気高さを与えている。 一八〇 神の光は愛であり、知恵であり、また親心である。 一八八 そして神を忘却したり、神に対する人類の子としての関係を誤認したりすることは、全人類における人倫と啓蒙と、そして知恵との一切の浄福力を破壊する源泉である。したがって人類は神に対して、このように子心を失うことは、世界の最も大きな不幸である。というのは、それは神の、父としての教育をすべて不可能にするからである。そしてこの失われた子心を回復することは、地上において失われた神の子たちを救済することである。」」(二二―二八頁から抜粋、現代日本語に改めた)
宗教信仰を感得する本(仏教3冊、イスラーム2冊、キリスト教3冊)キリスト教② :水谷周
要旨
宗教を紹介する書物は、図書館にも本屋にもネットにも溢れるほど見いだせる。そこでここでは、よく見る教科書的な紹介を繰り返すのではなく、筆者個人の目から見てその真髄を会得できるのではないかと思っているものを、多少選んで提供しようという趣旨である。それらが最善という意味ではないし、それ以外には見当たらないという訳でないことも自明の原理である。しかし個人的に心に響いたことなども含めて語ることで、読む人へも勘所が通じるのではないかという期待を込めて記すこととしたい。宗教信仰に関しては、直感が十分に働かないとどうしようもない面が強いので、このような経験的なアプローチを試みることとした。
2.『イエスの誕生』 (遠藤周作、新潮文庫、一九八二年。この他にも、『キリストの誕生』、『死海のほとりから』などは、姉妹作と言える。) イエスの存在に関して謎とされ、多くの議論がある部分に考察を加えて、理解を示している。それは作家遠藤周作の長年の悩みを踏まえた、キリスト教信徒としての解決を示していると言える。 ①犠牲の仔羊 「町から離れた寂しい谷に隔離された孤独ならい者(ハンセン病者)の群れのことも考えられたはずである。彼が出会ったあまたの病人たち、子を失った母親、眼の見えぬ老人。足の動かぬ男、死に瀕している少女、それらの人間たちの苦しみを分かち合うこと。一緒に背負うこと。彼らの永遠の同伴者になること。そのためには彼らの苦痛の全てを自分に背負わせてほしい。人々の苦しみを背負って過越祭の日に犠牲となり殺される仔羊のようになりたい。「その友のために」いや、「人間のために自分の命を捨てるほど大きな愛はない」それこそが人びとに無力に見えようとも、神の最高の存在証明なのだ。・・・彼は人々の永遠の同伴者たるために人間の苦痛の全てを背負いたいという願いが、神の意志と一致するのを感じられた。」(一〇四頁) ②エルサレム入場 「しかしそれだからと言って、受難物語の場面の悉くが事実のありのままを記述したのだと断定するのも危険である。どの部分が事実であり、どの部分が創作であるかは、それぞれの学者によって意見が違うが、その時、積極的にわたしがとる態度は一つである。私としては聖書の中の事実と真実との意味をはっきり区別したいのである。なるほど、この受難物語に見られるように聖書のなかには必ずしも事実ではなかった場面があまた織り込まれていることを私は認める。しかし事実でなかった場面もそれがイエスを信仰する者の信仰所産である以上、事実なのだ。それは事実などという枝葉末節のことをはるかに越えて、その時代の信仰者がそれを心の底から欲した場面であるから、真実なのである。恐らくイエスは驢馬にものらず、ひそかにこの都に死を決意して入ったのかもしれぬ。だがイエスの死後、イエスを忘れることができぬ人々はこのエルサレム入場の場面をゼカリヤ書九章九節の言葉に即して、救い主の姿を現す場面として華やかに描きたかったのである。彼等はイエスの無惨な死を目撃し、救い主ともある方がなぜ無惨な死にざまをされたかという問題と対決せねばならなかった。その彼らの苦悩がこういう場面を創らせた。いやそれは創らざるをえなかったのだから真実である。このことは小説家である以上、私は嘘ではないのだと言いたいのだ。」(一三〇頁) ③ガリラヤの大工 「ガリラヤという、小国ユダヤのさらに小さなパレスチナの田舎に育った大工はその短い生涯において弟子たちには遂に掴みえなかったふしぎな師だった。彼が何者であるかを彼等は師の死まで理解できなかった。弟子たちが彼を掴めなかったのは生きている間、われわれが人生が何かを理解しえないのと似ているのかもしれぬ。なぜなら彼は人生そのものだったからである。更に我々が生きている間神を把えられぬように、弟子たちにとってイエスはふしぎな人だったのである。彼の生涯は愛に生きるだけという単純さをもち、愛だけに生きたゆえに、弟子たちの眼には無力な者とうつった。だがその無力の背後に何がかくされているかを彼等が幕をあげて覗くためにはその死が必要だったのである。」(二二一―二二二頁)
『心の救済への道案内』 :玉田友昭
宗教信仰を感得する本(仏教3冊、イスラーム2冊、キリスト教3冊)キリスト教① :水谷周
要旨
宗教を紹介する書物は、図書館にも本屋にもネットにも溢れるほど見いだせる。そこでここでは、よく見る教科書的な紹介を繰り返すのではなく、筆者個人の目から見てその真髄を会得できるのではないかと思っているものを、多少選んで提供しようという趣旨である。それらが最善という意味ではないし、それ以外には見当たらないという訳でないことも自明の原理である。しかし個人的に心に響いたことなども含めて語ることで、読む人へも勘所が通じるのではないかという期待を込めて記すこととしたい。宗教信仰に関しては、直感が十分に働かないとどうしようもない面が強いので、このような経験的なアプローチを試みることとした。
キリスト教関係 1.『キリストにならいて』 (トマス・ア・ケンピス『キリストにならいて』岩波文庫、一九六〇年。) 著者のトマス・ア・ケンピス(一四七一年没、九二歳の長寿)はドイツのドュッセルドルフ近くの農家生まれ。黙想と祈祷に没頭する修道僧であったが、四〇冊ほどの著作がある。本書は第二の聖書とも言われて広く親しまれ、イエズス会の公式の教本となっている。 ①永遠で一つの言葉 永遠の「ことば」の語ることを聞く者は、雑多な意見から解き放たれる。この一つの「ことば」からすべて(は始まり)、またすべてがこの一つの「ことば」を語るのである。そしてこれが始め(第一原理)であって、また私たちに語りかけるものなのだ。誰もそれを欠いては、悟ることもできず、あるいは正しく判断することもできない。その人の眼にはすべてが一であり、すべてを一に納め、すべてを一の中に見る者は、心が確かに、また神の中になごやかに留まることができる。ああ、真理なる神よ、永遠の愛において私をあなたと一つにして下さい。多くを読み、また聞くことに、私は何度となく退屈に覚える。あなたのなかにこそ、私が望み願うすべてのものはあるのだ。」(一八―一九頁) ②学問と信仰 「この生におけるすべての完全には、何かの不完全さが付け加えられている。そうして私たちの観想はみな何らかの曇りのないものはない。謙遜に身をわきまえることの方が、深遠な学問の探求よりも、神に至る、よりたしかな道である。学問が非難されるべきものはなく、また何によらず、素直な物事の知識もそうである。それはそれ自体として見ればよいものであり、また神によって整えられたものである。けれど、良い良心と、有徳な生活は、つねにもっと好ましいものだ。しかしよい生活を求めるよりも、知識をえようと望む者が多い故に、それゆえ人はしばしば迷いに陥り、ほとんど何の収穫もえないか、えてもほんのわずかなのだ。」(一九頁) ③神こそ誇り 「たとえ富をもつとしても、それを誇ってはならない。また友だちのことを有力だからとて、誇ってはならない。むしろすべてを与え、かつ、そのすべてにも超えて自身をさえ与えようと乞い願われる、神を誇りとしなさい。身体の立派さや美しさの故に思い上がってはならない。それらはわずかな病によって毀され、汚し尽くされるのだ。自分の手腕や才能について自惚れを持たず、神意を損なわないようにしなさい。なぜならば生まれながらにあなたがもつすべてのものは、ことごとく神に属するのだから。」(二三―二四頁) ④悔い改めること 「もしいくらかでも向上しようと思うならば、神をつねに恐れつつしみ、過度の自由を求めてはならない。そして、すべての感覚を規律の下に制御し、ふさわしくない悦楽に身を委ねてはならない。こうして心の悔い改めに努めれば、まことの信心をえるに至ろう。悔い改めはいろいろな善い結果を生むが、放縦は何時もすぐそれらを失わせるのだ。私たちがみな追放の身である(楽園を追われてこの世へ来たこと)や、かくも多くの危難が魂(を襲う)のを想い顧みるとき、この世においてそもそも人が完全な喜びを覚える、というのは不思議なことである。」(四七―四八頁) ⑤死を思う 「もし一生の長さよりも、自分の死についてもっとたびたび思念するなら、疑いもなくあなたはもっと熱心に身を匡(ただ)し過ちを改めるだろうが。また将来受ける地獄の、あるいは煉獄の責苦を心底からよく見るなら、きっと喜んで悩みや悲しみも耐え忍ぶだろうし、どんなつらい目も恐れないだろうに。だが、それらのことが心に十分沁み込ないので(はっきり会得されないため)、また依然として甘い考えに執着するため、それで私たちは相変わらず冷淡に、たいそう怠けたままでいるのだ。(四九頁) ⑥神が中心 「どこにあなたがいようと、どちらへ向こうと、神に(心を)向かわせなければ、惨めさを逃れられない。なぜあなたは思い乱れているのか、望み願う通りに事が運ばなかったといって、自分の思い通りに万事がなるというのは、誰のことなのだ。私でもなければ、あなたでもない。また地上に住む誰かある人間でもない。この世では、何かの難儀や苦悩をもたない人というのは一人もいない。よし帝王だろうと、法王だろうと。では(他より)幸せというのは、誰のことだろう。たしかにそれは神のために事をしのびうる人に違いない。」(五〇頁) ⑦死と隣り合わせ 「明日には、自分が夕方まで行き着けまい、と思い見なさい。また夕べが来たらば、明日までの生を約束されているなど、敢えて思ってはならない。それゆえ、何時も用意を怠らずに、死に不意打ちを食わされぬような生き方をしなさい(ルカ・二一の三六)。不意に、また予期せぬ時に、死ぬ者が多い。なぜというと、「思いがけない時分に人の子は来るだろう」から(マタイ・二四の四四)。この最後の時が来た折には、あなたは自分の過ぎ去った全生涯を(今とは)まるで違った風に考え始めて、ひどく悲しむだろう。自分がそれほど怠慢で、だらしがなかったことを。」(五四頁) ⑧神への帰依 いかなる被造物からも、慰めを求めない、というところまで人が到達したとき、そのとき始めて、彼は神を完全に会得しはじめるのだ。そのときはまた、どんなことが起ころうとも、十分満足していられよう。そのときには、大事について喜びもしなければ、小事について悲しみもしないだろう。ただ神の手に自分をのこりなく、また信頼にみちて、任せまつるのである。神こそ、彼にとってはすべてに在ってすべてであり(ローマ・一一の三六)、どうあろうと神にとっては何も滅びも死にもすることがなく、万物が彼のために生き、そのうなずきにためろうことなく従いつかえるものなのである。」(六四頁) ⑨感謝 「それゆえあなたは、ごく小さいことについても感謝しなさい。そうすれば、さらに大きな(賜物)をうけるにふさわしいものになろう。ごく小さなものをも、あなたは大層立派なものとし、ごくつまらないものを、特別な賜物と考えるよう。もしあなたが、与え手の尊さを認めるならば、どんな贈物と言えども、小さいとか、とても下らないとか、見えることはなかろう。けだし、至高の神の与えられるものならば、どんなものでも、些細ではないはずだから。たとえその与えられたものが罰や筈であったにしても感謝すべきである。なぜならば神が私たちの身に起こるのを許されることは、何であろうと、いつも私たちの救いのためになさることだからである。神の恵みを保っていこうと願うものは、恵みが与えられれば、それを感謝し、取り去られれば、それを耐え忍び、それがまた帰ってくるよう祈るがいい。そしてよく要心して身をへりくだり、(神の恵みを)失わぬようにしなさい。(八八―八九頁) ⑩真理の下で 「それ故お前がする仕事のどれからも、みな大したこと(をした)とは決して考えてはならない。永遠なるもの以外には何一つ、大したものとも、貴く感心すべきものとも、もてはやすに値するとも、考えうべきではない。何も高尚だとか、本当に称賛し乞い願うべきものと、思ってはならない。永遠の「真理」をあらゆるもの以上に愛し、自分のこの上ない卑しさを絶えず厭離するよう。お前は自分の不徳と罪過を何よりもはげしく恐れ、責めて非難し、かつ避けるがいい。」(一〇七―一〇八頁) ⑪神に仕える楽しさ 「ああ、神への奉仕の何という快さ、嬉しさ(マタイ・二の一〇―一二、ヨハネ・五の三)、それによって人は本当に自由にも聖いものにもなり得るのです。ああ、教えのために仕えるのは、何と聖いつとめでしょう。それこそ人を天使たちにも等しいものとし、神の御心に適わせ、悪魔には畏怖すべきものとし、すべての信者たちの範ともするものです。ああ、この勤めこそ私たちが願いもとめ、常住望み取るべきものです。それによって最高善もかちえられましょう。またはてなくつづく喜びも得られるのです。」(一二二頁)
宗教信仰を感得する本(仏教3冊、イスラーム2冊、キリスト教3冊)イスラーム② :水谷周
要旨
宗教を紹介する書物は、図書館にも本屋にもネットにも溢れるほど見いだせる。そこでここでは、よく見る教科書的な紹介を繰り返すのではなく、筆者個人の目から見てその真髄を会得できるのではないかと思っているものを、多少選んで提供しようという趣旨である。それらが最善という意味ではないし、それ以外には見当たらないという訳でないことも自明の原理である。しかし個人的に心に響いたことなども含めて語ることで、読む人へも勘所が通じるのではないかという期待を込めて記すこととしたい。宗教信仰に関しては、直感が十分に働かないとどうしようもない面が強いので、このような経験的なアプローチを試みることとした。
2.『溢れる随想』 (前掲書『現代イスラームの徒然草』。) 次いでは近現代であるが、それを二〇世紀エジプトのイスラーム思想家アフマド・アミーン(一九五四年没)の随筆集に見てみよう。何世紀経っても物事の本質は判明しないままであり、人生の目的も何も判明しない。それはいわば、人類史の憂鬱である。他方、科学の進歩は目をみはるばかりで、それは直ちに宗教への挑戦と受け止められた。さらに二度にわたる世界大戦という人類の将来を疑うこととなるような惨状を目前にした。宗教、そして信仰心の立場と役割は何か。こうした疑問がイスラーム圏でも湧いてくるのは当然であった。 ①知ることと知らないこと 人はなぜ存在するかという本質論への回答はないままに、一生を過ごすことが運命付けられている。絶対主の知恵を明らかにすること、この謎解きそのものが創造の目的ととらえることはできないのか。そうすることでようやく生きることの目的と生きがいが生まれてくるというのである。 「よく知らない人が知っているといい、よく知っている人が一番知らないと言う。無知な人や、あるいは逆に識者でもその多くは、何でも簡単明瞭で、理解や解釈もできるとする。しかしこの存在について、何が分かっているのだろう。その外側しか、われわれは知らないのではないか。その真実や深みについては、ほとんど知らないのだ。いつこの戸惑いが終わるかを知っているのも、神だけなのだ。・・・ そこで次の質問が出てくる。「人間はどうしてこの世に存在するのか?」それは 解くことができない謎に包まれている。人は物質の外側を知っても、その核心を知ろうとすると、当惑するのみである。物質の裏側の神的な部分に関しては、ますます当惑することとなる。・・・ 世界は解かれることが待たれている謎に満ちている。それは無声映画のようで、画像すべてが理解されるわけではない。人類と世界の創造以来、さまざまな偉大な人たちが現れた。啓示を教える預言者だとか、自然美を称える詩人であるとか、研究し分析し結論付ける学者であるとか、可能と不可能の全ての諸側面を深めては交代させて研究する哲学者であるとか、存在の本質を知ることができない論理や知識の失敗を認識して、嗜好と直観による霊知を主張する神秘主義者であるとか、かれら全員が人間に正しい知識と疑問も湧かない諸課題を明示した。しかし存在の本質は知ることがなく、われわれはその解明を待っている。実にいくつかの物語の場面は解説しても、その本質と含蓄と秘められたところは、まだわれわれにとって不明なままなのである。・・・ 他方で、こう言うこと(捉え方)もあり得るだろう。つまり、世界は人間が謎解きをするが、別の目的のために創造されたとするのである。換言すれは、理性を含む世界の創造(の目的)は、その背後にある(絶対主が有する)知恵を(顕示する)ために創造されたとするのである。そうすると異見を唱えること自体が、馬鹿げたことということになる(人の理性は創造の在り方を議論するものではない)のである 総じて人がもしもこの曖昧さに味を覚え、謎解きの試みをして、時に成功し時に失敗しているならば、この曖昧な雰囲気の中で、強くて明白な味わいを享受することは悪くないのである。」(八―一七頁) ②宗教の世界 人は天に向かって直観するとして、天から人に向けられるのが啓示である。いずれも絶対主が選択されるものだが、人の「心」が基軸であるとされている。これは現代の日本語だと、宗教的天分と言い換えた方が分かりやすいかも知れない。他方、天分があるから教えが伝えられるのであれば、伝えられる人に天分があるというのと、同義になってしまう。やはり「心」が基軸であるとするので十分なようだ。 「宗教の基礎は、この物質世界の裏には、精神世界があるということである。それは幻想や詩的な王国ではない。それは存在すべてに関する、真実の王国である。つまり美、植物、動物、そして人間などすべてである。その精神性の薫香は、最高の魂であるアッラーからのものである。 「かれ を、称賛(の言葉)をもって賛美しないものは何もありません。ただしあなた方は、それらがどのように賛美しているかを理解していません。 」(一七:四四) 感じようが感じまいが、何事にもその精神的なメッセージがあるが、それは精神性において異なっている。それが異なる様子は、各世界の個人や各グループの事柄が異なっているのと同様だ。それはあたかもピアノの調子に強弱や剛柔や高低の違いがあるのと同じだ。自然の存在の中には、段階というものがある。身体、家族、軍隊、山河や丘や樹木と花々の集まり、あるいは太陽系の星々など、いずれもそうである。どれにも高低の段階がある。それに気づいたのはダーウィンであるが、かれは進化論を唱えた。どのグループにもその部分より価値や機能が一段と高いというボスがいる。それがその種を代表するということになる。精神界でも同様であり、この価値の差があり、この様々な段階がある。この段階こそは、上ってゆくアッラーへの道のりである。 この精神界の個々人は、感性、愛情、熱情、そして最高の魂の光を受け止められる能力において差異がある。そして啓示と直観を受け止める能力の差がある。宗教では、それを光で示すことがよくある。太陽は光を発射し、月はその光を受け止めて地球に送る。またその周辺の星々や星座に対しても、位置など受け付ける条件次第だが、やはり光を送っている。これは精神界における精神的な意味合いの表現として、適切な例えになる。・・・・・ この最高の魂(アッラー)は、すべての知識、能力、知恵を集める王国の長であり、望むものを望む者に対して与えるのである。(預言者の)それとの関係は、月と太陽であり、光を受けてそれを放つのである。あるいは受け入れて、発出する。(通常の)人は預言者ほどでなくて、自分では(啓示を)受け付けないのである。またかれらに放出されたのではないが、(預言者から聞いて)放出する。これらは、精神界の諸法を人間の舌で説明することになる。かれらは苦痛を受けて、また誤っている人間性の叫び声に対する応答である。あるいはかれらは、傷付いた人間性に対する妙薬である。またかれらは、用意のある人は誰でもが分けてもらえる、光を広める者である。その人の言葉で、そしてその人が受容できた範囲で、宣教しているのだ。その言い方で、また心に対して広めていた光でもって、人々に影響も与える。だから多くの信者たちは、信じていたのは、支援であって議論ではなかった。「何だ、これは嘘つきだ」という人もいた。かれら宣教者は、人の心に光を投げかけていたので、理性で説得する方が少なかった。かれらは身体と欲望と地上の争いが集まると、人々の心を天上に(説諭で)高め、過ちが明らかになるのに合わせて、その社会を改革しようとした。かれらの教えで種子を撒いて、事後にそれらの過ちに気付いて修正するための指導をしたのであった。 最高の魂は、誰が啓示と直観に向いているかの選択をする際に、物質世界で気にするような、威厳、資産、血縁、知識、あるいは教育などには気もくれなかった。その選択には心だけが重要で、そのメッセージをどこで表すべきかについては、最もよく知っておられるのだ。」(一四七―一五〇頁) ③科学と宗教 近代以降の宗教に対する最強の挑戦は、自然科学の発達であった。そしてそれに基づく西欧文明はイスラームに対する挑戦と映った。二つの異なる人間の活動であり、それぞれに固有の方法があると主張している。最終的には絶対主の知恵を明らかにするのが、創造された人間の責務であるということになるのであろう。 「・・・もっとひどい科学者の間違いは、観察、実験、そして証拠という手法は唯一なものであると考えたことである。世界の全ては科学で解決され、科学の方法に則ると考えた。確かにその手法によって正しく世界の車輪に向かうことはできるかもしれないが、しかしそのエンジンには迫れないのだ。思考を詳細にして深める人は、その研究を車輪という物質で止めずに、その背後のあるものに迫るのだ。・・・これらも真実であることは、否めない事実である。科学的な方法だけに依拠するのは間違いである。芸術の方法は、直観と精神の純粋さと心が開かれていることに依拠している。それは科学の方途と同様に、正しいものである。あちらにはその領域があるように、こちらにも否定されない聖域があるのだ。世界理解のために科学的方法だけに限るのは、明らかに変則歩行である。・・・ この科学と宗教の間の根深い争いの根本原因は、私には分からない。科学者は神経質となり、かれらの知識はすべてに関係しており、あらゆる問題を解決するとして、知識以上に求めるものはない、だからかれらの領域以外には領域はないとするのである。宗教家の方も神経質になり、科学の領域での知識を信用しないで、また宗教の根幹と小枝部分の峻別ができずに、先達の言葉は降ろされた啓示のようなものとして固く取りつかれてしまったのである。・・・真実の科学と宗教は、その目的を一つとしており、それは真実への愛情である。手段が異なってはいるものの、両者共、人間性でもってその完璧な姿に到達するであろう。そして周囲で取り巻くものも理解するのだ。あちらは物質的に、そしてこちらは精神的にするのである。」(一六〇―一六九頁) ④宗教の将来 第二次大戦の惨状を前にして、アッラーの支配を説くことに時代錯誤的な違和感を持たせられる向きがあったのであろう。そこで本論は、どのような状況であれアッラーの支配は徹底されていることを再確認する趣旨である。大規模な天災もアッラーの差配なのであり、その事実を揺るがせにしないということになる。 「アッラーが世界を支配し統御されるのは、広い一般的な法(摂理)に拠るのであって、狭い部分的なものではない。人を創造しその一般法に従うようにされ、それに従わない者は一掃された。過去、現在、未来を知り、この世とあの世を知り、星座もわれわれ以外のものも知っておられる。総体的な法に反している家の一部分を見るように、アッラーに対するのは、視野を狭くしていることになる。・・・ アッラーはその一般法から人間に意思の自由を与えられ、自然に行動から生じる部分を授けられたのであろう。また兄弟の命に関する人の責任もそうだが、それはちょうど一部の細胞は他の細胞にも責任を負っているのと同様である。これが世界の一般諸法を平等に扱う一般法であるならば、不満不平は何ら主張の根拠はないということになる。・・・ 右に見た見解が、この戦争があまりに悲惨であることに鑑みて、どうして人々の間に広まらないことがあろうか。それはアッラーが世界に広められた一般法に基づくものでもある。世界はその一般法と調和するであろう。またそれに拠らなければ、その罪を問われることになるし、自らの慢心を是正することもできない。物質主義の誤りは明らかとなり、アッラーに関する見方も改められることは、既に述べた。そうすれば死は生命の復活につながり、それは良いことである。またそうすれば、罪人を正すことになるので、懲罰は慈悲であるということになる。それは愛情だということだ。われわれはこの方向に傾く。将来のことは、アッラーが一番ご存じである。」(一二八―一三八頁)
『ケアの時代 「負の感情」とのつき合い方』 :鎌田東二
『南方熊楠と宮沢賢治 日本的スピリチュアリティの系譜』 :鎌田東二
宗教信仰を感得する本(仏教3冊、イスラーム2冊、キリスト教3冊)イスラーム① :水谷周
要旨
宗教を紹介する書物は、図書館にも本屋にもネットにも溢れるほど見いだせる。そこでここでは、よく見る教科書的な紹介を繰り返すのではなく、筆者個人の目から見てその真髄を会得できるのではないかと思っているものを、多少選んで提供しようという趣旨である。それらが最善という意味ではないし、それ以外には見当たらないという訳でないことも自明の原理である。しかし個人的に心に響いたことなども含めて語ることで、読む人へも勘所が通じるのではないかという期待を込めて記すこととしたい。宗教信仰に関しては、直感が十分に働かないとどうしようもない面が強いので、このような経験的なアプローチを試みることとした。今回はイスラームの第1回。
イスラーム関係 1.『随想の渉猟』 (イブン・アルジャウズィー『黄金期イスラームの徒然草』水谷周編訳、国書刊行会、二〇一九年。) まずはイスラームの全盛期とされる、一二世紀アッバース朝時代の高名なイスラーム説教師であり法学者イブン・アルジャウズィー(一三〇〇年没)の徒然草のような随筆集である。イスラームの識者が随筆を書き残したのは珍しいが、彼らの飾らない心情をうかがうには好材料となっている。 ①川の水と乾パンが昼食 今でいうと厳しい受験勉強をしているような禁欲的な生活の中で、イスラームの学習に励んだことが分かる。家はそれなりに裕福な家庭であったが、それでも今では考えられないほどの生活レベルであったようだ。しかしこのような質実剛健な生活ぶりは、信仰心の鍛錬とは別物ではなかったということが、手に取るように伝わってくる。何よりもそれを自らが求めたことであったとしている。 「私は自分が求めて望んだために、知識を求める甘美さにどんなきついことが含まれていても、それは蜂蜜よりも甘いものとなったのであった。子供のころは、預言者伝(ハディース)の勉強のために乾いたパンを一切れ持って家を出た。そして(旧バグダッド近郊の)イーサー川のほとりに座ってしか、それを食べることはできなかった。というのは、一口食べては川の水を飲んでいたのだ。その時でも私の目は、知識の獲得に燃えていた。その成果は、預言者伝承や預言者(アッラーの祝福と平安を)の事情とその作法、あるいは教友や従者たちのそれらを多数聞いて、私はすっかり預言者の道に関しては、イブン・アジュワド(彼の名前は川と同じでイーサーだったので連想したのであろう。彼はアラビア半島ナジド地方の初期の法官)のようになっていたのであった。」(一六一―一六二頁) ②権力者から離れろ 知識を売るのは、信仰も売っていることになるとの戒めである。禁欲は大きな徳目として、イスラーム道徳で扱われる。 「裁判官や語り部は、生活が苦しくなるとすぐに支配者の下へと逃げ込んでしまう。それは金銭目当てだが、支配者は現世を正価で獲得することもなければ、あるいはその正価で支出することもない(盗んだり、悪用したりする事)。・・・ 学者が直面する初めての問題は、知識による収入が得られないということであろう。ある正当な信者が、ヤハヤー・ブン・ハーリド・アルバルマキー(八六〇年没、ハールーン・アルラシード治世の大臣)の家から男が出てくるのを見た。そしてその男が言った。「益をもたらさない知識から、アッラーのご加護を祈る。」その学者は、禁止されたものを見ても拒否せず、不正に得られたものを食べるので、その心は封じられ、至高なるアッラーとの甘美さもなくなり、誰も彼から指導を仰がなくなった。・・・ 私は生涯を通じて俗欲を捨てて、現世の喉の渇きに耐えた人びとのために犠牲になるのである。彼らは死後、喜悦の飲料を飲み干すし、彼らの事績は語り継がれ、その物語は心の渇きを潤し、そのカビを磨き落とすのである。・・・ 忍耐にも忍耐を、支援され成功する者よ、現世で栄える者を羨(うらや)むな。そのような富を考えれば、あなたはすぐに信仰の門から見たときには、それは狭いものだと気が付くだろう。また自分に解釈上甘くすることなかれ。この世のあなたの生涯は短いものだ。・・・もし忍耐の緒が切れそうになることがあれば、禁欲者たちの話を読むといいだろう。もし心に関心と覚醒が残っているならば、それで教えられ、恥じらいを覚え、あるいは破滅させられるだろう。」(二一九―二一二頁) ③説教の効果はさまざま 説教の効果は人さまざまのようだ。少々ユーモラスに描かれている。またその書き振りからして、説教をどのように受け止めるかはかなり幅を認めていることも分かる。そのような緩さを信仰心に認めるのが自然であり、息長く持続させられるということになるのであろう。 「説教を聞いて心が目覚めても、それが終わるとすぐに心は堅くなり、不注意が舞い戻ることがある。人の心はさまざまであるが、説教の前後で変わるのには、二つ理由がありそうだ。一つは、説教は鞭打ちのようなもので、それが終わればその痛みは消え去るということ。もう一つは、説教を聞くときの人の心身の状態は、世俗から離れて没頭しているが、それが終了すると雑事にまみれるのである。そこで正しい姿勢から離れることとなる。 これが多くの人の場合であり、目覚めの影響がどのように残るかは、人によりけりなのである。人によっては全く迷わずに、確固とした姿勢を保つ。そうする場合は性格からして、たとえそうすることが邪魔な障害となってでも、そうするのである。ハンザラ(・ブン・アビー・アーミル、六二五年没、マディーナ住民で預言者ムハンマド支援者)という男は、自分は偽信者(説教で自戒の念が湧いたため)だと言って自分を責めたことがあった。 そうかと思うと羽毛のように風に舞って、性格上時に不注意となり、あるいは時に説教通り行動する人もいる。あるいはまた、石の上の水がなくなるように(すぐ流れ去るが)、耳にした分量だけは遵守する人たちもいる。」(一四―一五頁) ④学問の目的は、アッラーを愛すること 勉学の目的はアッラーを覚知することと明言している。諸学の百貨店に目を奪われないようにと、アッバース朝の時代に警告が出されているのだ。学問と信仰の関係についての見地として、一枚起請文を想起させるところもある。 「人によってはクルアーンの読誦法に没頭して、それだけで一生を浪費する。その人は主な流儀に依拠しておけばいいのであって、枝葉に拘る必要は毛頭ないのだ。クルアーンの読誦者が法学のことを聞かれて、何も答えられないというのは何とも情けない話だ。クルアーン読誦法がさまざまあることに、忙殺され過ぎているのだ。 人によっては文法学や、さらには言語学だけに没頭している。あるいは預言者伝承を集めては書き立てて、少しも何が書かれているかについて頭を巡らせていない。伝承学の大家で礼拝に関して聞かれて、何も答えられなかった人もいる。それは読誦者、言語学者、そして文法学者についても言えることだ。・・・だから必要なことは、まずそれぞれの諸学より少しずつ学んで、その後に法学を学ぶことである。そうして諸学の目的を知ること、つまりその目的とは、至高なるアッラーを学び、その覚知(認識)を果たし、そしてアッラーを愛することである。 星についての知識で一生を棒に振るのは、全く馬鹿げている。それは少々学び、時間を知るようになればいいのだ。(星占いで)運命や判断などと言われることは、無知以外何ものでもない。それらを実際知ることはありえず、試みても彼らの無知をさらけ出すだけである。・・・化学に専念するのも馬鹿げている。それは全く夢想であり、黄金が銅になることがないと同様に、銅が黄金になることもない。それをしようとする人は、人々を硬貨に関して惑わせるだけである。もちろんそれが、その人の目的であるかも知れない。・・・権力者には用心して、預言者(アッラーの祝福と平安を)と教友と従者の道のりに関心を払って、精神の鍛錬に励みつつ、知識に則る行動を取らねばならない。真実に従う人は、彼を真実が支援するのである。」(二一一―二一三頁)
『現代イスラームの徒然草』 :アフマド・アミーン
『黄金期イスラームの徒然草』 :イブン・アルジャウズィー
『負の感情』とのつき合い方 :鎌田東二②
『負の感情』とのつき合い方 :鎌田東二①
宗教信仰を感得する本(仏教3冊、イスラーム2冊、キリスト教3冊)仏教③ :水谷周
要旨
宗教を紹介する書物は、図書館にも本屋にもネットにも溢れるほど見いだせる。そこでここでは、よく見る教科書的な紹介を繰り返すのではなく、筆者個人の目から見てその真髄を会得できるのではないかと思っているものを、多少選んで提供しようという趣旨である。それらが最善という意味ではないし、それ以外には見当たらないという訳でないことも自明の原理である。しかし個人的に心に響いたことなども含めて語ることで、読む人へも勘所が通じるのではないかという期待を込めて記すこととしたい。宗教信仰に関しては、直感が十分に働かないとどうしようもない面が強いので、このような経験的なアプローチを試みることとした。
3.『壺坂観音霊験記』 (原作は作者不詳の浄瑠璃、一八七九年に大阪で初演。『壺坂霊験記』、東京創元新社、昭和四四年。名作歌舞伎全集第七巻。) 明治初年頃の浄瑠璃であるが、歌舞伎や講談にもなった『壺坂観音霊験記』というのがある。ユーモアも交えて、海外公演もされるほど好評を博した。その筋書きは次のようである。あまりに信仰というものは、その人が滝壺に投身するほどの決意の問題であることを象徴的に示しているので、ここで触れることとする。 座頭の三味線弾きである沢市は、妻のお里が明け方になると出掛けていくのに気付き、不倫について疑いを持ち、妻を問い詰める。お里はこの三年間、沢市の目が治るようにと壷阪寺の観音様に願掛けに行っていたと打ち明ける。邪推を恥じた沢市は、お里とともに観音詣でを始めるが、目の見えない自分がいては将来お里の足手まといになると考え、満願の日にお里に隠れて滝壺に身を投げる。揃えて残された草履から夫の死を知り悲しんだお里も、夫のあとを追って身を投げてしまう。そうすると二人の夫婦愛を聞き届けた観音の霊験により奇跡が起こり、二人の命は助かり、沢市の目も再び見えるようになる。そしてお里の美貌に沢市は驚かされるという一幕もある。
宗教信仰を感得する本(仏教3冊、イスラーム2冊、キリスト教3冊)仏教② :水谷周
要旨
宗教を紹介する書物は、図書館にも本屋にもネットにも溢れるほど見いだせる。そこでここでは、よく見る教科書的な紹介を繰り返すのではなく、筆者個人の目から見てその真髄を会得できるのではないかと思っているものを、多少選んで提供しようという趣旨である。それらが最善という意味ではないし、それ以外には見当たらないという訳でないことも自明の原理である。しかし個人的に心に響いたことなども含めて語ることで、読む人へも勘所が通じるのではないかという期待を込めて記すこととしたい。宗教信仰に関しては、直感が十分に働かないとどうしようもない面が強いので、このような経験的なアプローチを試みることとした。
2.『観音の霊験』 (中野環堂『観音の霊験』有光社、昭和15年。『観音全集』全8巻の第3巻。) 珍しい本を取り上げてみる。戦前の出版だが、当時の宗教学者が取りまとめたもので、一般人の観音体験、著名人の信仰、逸話集などから構成されている。現在でも電子書物化されており、それなりの関心は集めているようだ。観音菩薩は法華経に説かれるが、古くより衆生救済の菩薩として人気があり、各地に観音像が見られることは誰しも知っている。この書籍より幾つか印象深い個所を見てみよう。現代日本語に置き直して記述する。 ① 一心一向の信仰 観音信仰に入った一つの契機と、その信仰に基づく覚悟について、編者自身が次のように述べている。彼は一人米国の病院に入っている間のことである。 「「南無大慈大悲観世音菩薩」こう念じると、今までの淋しさもなくなれば、悲しさ、やるせなさを忘れてしまった。観音さまを念じることによって、私は身内の者や、恋人が訪れてくれたにもまさる喜びを味わうことができたのである。私は慰められた。これが、私がある意味において観音さまを信じるようになった動機である。寂しい、悲しい、やるせない、病中のこの逆境が私を信仰に導いてくれたのである。」(29頁) 「私は病気でどんなに苦しんでも、その間「直してくれ、直りたい」と思ったことはない。死ぬも寿命なら、生きるのも因縁である。仏様の御心のままだ。何もくよくよするに及ばない。ただ無念無想、精神を統一しているだけである。これが、病気にもよいのであろう。私の病気が手術もせずに、ケロリと直ったことは、現代医学からみるとたしかに不思議であり、奇蹟である。しかし、私にはこんなことが常にある。」(32頁) ② 某海軍中将の観音霊験 沈没艦船から数名の乗員を救うことができて、観音信仰に入った後、都内の看護学校において次のように述べて、観音信仰の精神を語った。 「「観音さまは慈悲の菩薩である。慈とは与楽であり、悲とは抜苦である。苦を抜き楽を与えるのが、皆様の天職であるが、それは観音さまの御心と同じなのであるから、どうか皆様も観音さまとなって、世の人々を救ってあげねばなりません」と。とにかく、観音さまは現世の救いがあるからありがたい。現代人の生活にぴったりくるのである。私は、ただ迷信に堕せぬようにと考えて、観音信仰を実践している。」(66頁) ③ 品川高等女学校長代理漆雅子女史の観音霊験 「先年も洋裁室が漏電のため、まさに大火になろうとしたが、不思議に一坪ばかりこがしたのみで消し止めることができた。これも一つに観音信仰の利益であろうと信じ、まことに有り難いことであると思う。道理に合わぬ、学問的でない、科学的でない、と言って私の話を一笑に付される方があれば、それも結構である。しかし私は信仰というものは絶対的なものであると思い、理屈がましいことは抜きにし、聖天様ないし観音様はありがたいものであると信じ、ただ涙を流している次第である。とにかく、信仰に理屈は必要でないと思う。信ぜずにはいられない、そしてただひたむきに信じていると、御利益は願わなくとも、いろいろ有難いこと、もったいないことが終始体験できると思う。」(133―134頁) ④ 大妻高等女学校校長大妻コタカ女史の観音霊験 「私どもは霊眼がないから、見えないことが数多くあるけれども、神様の方からは善きも悪しきもみんなよくお分かりになっておられる。人が見ているから、いないからと区別はすまい、また人が何と言おうと書こうとかまわない、正しく行ってゆくばかりだと決心したのも観音信仰からであります。・・・私の今日あるのは、その他の神様のおかげもありますが、観音様のおかげーご加護とお導きーが特に大きいことを思います。感謝の心で過ごしている次第でございます。」(137―138頁) ⑤ 東京女子商業学校長嘉悦孝子女史の観音霊験 「世の中がだんだん物質万能にかたよって来るようですが、物質ばかりでは決して人間の安心も幸福も得られるものではありません。物質はかえって悩みのたね、それを離れさせてくれるものは信仰であります。信仰する者には常に感謝と喜びがあります。・・・ (車中に普段は使わない肩掛けを忘れてきて)私は自動車番号も覚えておりますから、探せばすぐにわかるとは思いましたけれども、「よけいなことをしたから、仏様がそうしたものをしないでよいというので、お取り上げになったのでしょう」と申しそのままにいたしました。こう考えられるのも信仰のおかげで、少しも惜しまず、心にわだかまりもなく、かえって御戒めを有難く思って感謝しております。」(150―151頁) ⑥ 死刑囚の話 昭和八年に市ケ谷刑務所で死刑が執行された。極悪の人殺しとされた藤吉という名前の男であったが、その最後は観音経を携えていたという。 「死刑立会人の話によると、藤吉の死はあまりに立派であった。午前9時監房から引き出すと、「どうかしばらく待ってください」と言う。何をするのかと見ていると、ちゃんと帷子に着替え、静座して観音経を一度高らかに読誦し、それから右の手に数珠、左の手に観音経をもってしずしずと、何の不安もなく、何の未練もなく、断頭台に上って行った。死に着くこと帰するがごとく、悠々として不安もなく、畏れもないその悟りきった姿を見たとき、人々はなんと言ったか。「ああ、あれが、極悪の人殺しまで犯した大罪人であろうか!」彼は死の直前、人々に向って言った。「私のような者でも、きよらかな者となることができました。どうか、悪い人々を善い方に導いてください。」彼の心からなる懺悔、真心の叫びはどんなに人々を感動させたことでしょう。(その遺言は)わが心、今より後は、出流山(栃木市)の、地蔵となりて、人を導く」であった。(162―163頁)
宗教信仰を感得する本(仏教3冊、イスラーム2冊、キリスト教3冊)仏教① :水谷周
要旨
宗教を紹介する書物は、図書館にも本屋にもネットにも溢れるほど見いだせる。そこでここでは、よく見る教科書的な紹介を繰り返すのではなく、筆者個人の目から見てその真髄を会得できるのではないかと思っているものを、多少選んで提供しようという趣旨である。それらが最善という意味ではないし、それ以外には見当たらないという訳でないことも自明の原理である。しかし個人的に心に響いたことなども含めて語ることで、読む人へも勘所が通じるのではないかという期待を込めて記すこととしたい。宗教信仰に関しては、直感が十分に働かないとどうしようもない面が強いので、このような経験的なアプローチを試みることとした。
仏教関係 1.『禅に生きる』 澤木興道(誠信書房、昭和31年) 座禅を組んで何を悟るのかについては、幾多の解説書や、古来の教本がある。しかしそれが生きた形で語られているところに、この書物の魅力と独特の説得力があると思われる。著者の澤木興道(1880―1965)は三重県津市の人であったが、全国を行脚して「宿なし興道」ともいわれた。「寺も、金も、名誉も持たぬ」をモットーに一生を雲水の生活と修行に捧げたことで知られる。彼の言行録をまとめた本書は赤裸々な信仰告白ともなっていて、一言一句がゆるがせにできない迫力に満ちている。真の信仰を求める者の姿勢には、宗教の如何を問わず学ぶべきものが多いことを知らされる。ただし漢語が横溢し現代語でないところが多いので、以下では注目される諸点をまとめ筆者の注を随所に付けた。 ① 遊郭に育つ 遊郭が最上の教育環境だったそうだ。ただ驚かされるだけだが、それ以上の注釈は不要であろう。「人間は、内緒ごとはできんぞ、これがそのときの実感であった。このおやじはまさかこんなところで死ぬつもりはなかったろう。家を出るときには、何か用事があるような顔をして、すまして出てきたことであろう。「今から娼婦買いに行ってくるよ」と妻に断ってくるはずないにきまっている。」(8頁)(注:両親を亡くして孤児となった後、彼の養家は遊郭にあった。) 「わしがこんなふうに無常を観じたのは、環境が環境であったからである。養家の生活環境というものは、この世の中の最悪、最下等のどん底で、人格だの教育だのということとは縁もゆかりもないところだったが、実はそれが却って最上の教育環境であったようだ。」(10頁) ② 道を求めるはじめ 「千秋さんばかりでなく、その家族全部の人たちの雰囲気に何となく清らかなものを感じて、いつの間にか自分自身の中にも「道を求める」というような観念がはぐくまれていた。」(15頁) 「世の中に金や名誉よりも大切なものがある」と知ったのは、まったく千秋さんが色々な話をしてくれたり、色々なことを教えてくれたお陰だった。そして、これがとうとうわしの一生を決定した。」(16頁)(注:森田千秋は近所の日本画家) ③ 無我を知る 「むしろ自分の要求を捨ててしまって、この身ぐるみ全部を他人のために使い盡していくのが本当だ。我々はいつ死ぬかわからぬが、要するに人のためになったというだけが人生の意味だ。・・・真宗の寺へ、よくお説教を聞きに行った。そこでは、こんなことを「無我」というのだと知らされた。そのことは坊さんになって、ひたすらこの道を求めたいという気持ちにまでだんだんせりあげていった。」(25頁) ④ 雪山童子の求道の話 「諸行無常是生滅法、生滅滅己寂滅為楽」(28頁)(注:真実を教えるという悪鬼が腹が空いたと言うので、自分の身を食べてもいいからその真実を求めたという雪山に住む童子の求道心の逸話。童子が木の上から身を投じた瞬間に鬼は菩薩に戻って、童子を救って助けたという。イスラームの似た話は、神の命令により息子を犠牲にすることを決意した瞬間に預言者イブラーヒームは赦されて、代わりに羊を犠牲に付したという。) ⑤ 既成宗門の無気力さ 「すなわち、あつかいやすくて、飼い慣らしの楽なのを可愛がり、骨と意気地のあるものをひどく嫌った。もっとも今日になってみると、この風潮の方がむしろ一般的で、宗門一般が無気力になってしまっている。そういうふうでは、ピチピチした弾力のある、いきのいいのを教育しきれないのだ。そこに、形式化して迫力を喪失した既成宗門の無気力な実態が露呈されていると思う。」(62頁) ⑥ 人間塞翁が馬 「してみれば、何がいいのやら悪いのやら、何が幸なのか不幸なのか、にわかに決めてしまうわけにもゆかないのである。」(66頁)(注:師匠に嫌われて他へ送られたことで、真に随身する師と出会うことができたという顛末) 「わしの顔さえ見ると、「金、金、金、金」と、無心をする以外には何も言うことはなかった。思うに、わしが堕落することができなかったのは、実にこの「あきれた養父」のお陰である。」(93頁) ⑦ 人間の本音 「人間というものはドタン場まで行って見なければ、ほんものの実物にはつき当たらぬものである。平常如何に実物をお留守にして、にせものを作ることにのみ苦労しているかということが、手にとるようによくわかった。」(84頁)(注:日露戦争の際、満州の戦場で日ごろ威張っていた将校が敵弾の下で怯える様) ⑧ 生と死 「事実、生きていたほうがよかったかどうかは、一生を通じて見なければわかるものではない。わしはいつも自分の生命というものを、むかしも今も変わらず、かく透明に見渡してきている。」(99頁) ⑨ 他宗門での緊張 「当時のわしはずっと他宗門(注:奈良法隆寺勧学院(聖徳宗)で勉学)にいて、骨の髄までそれに染まりたくない、どこまでも永平門下(曹洞宗)の節操を保持しようと一生懸命だった。・・・それが、後の蘆庸宮の空寺における3年間の閉関坐禅にまで純化されていったのである。」(131頁)(注:この精神的な葛藤が、3年間の孤独の修行の原動力となった。) ⑩ 信仰と真実の生活 「わしはいつも「出家とは自己の生活を創造するものである」といっているが、今の坊さんたちも、折角、仏門に身を置いたのだから、細君があるならあるでいい、子供があるならあるでいい、そのままでいいから、めいめい信仰というものをもって、真の仏道体験から割り出して自分の今のこの国での生活をいきいきと創造して、真実の生活をして貰いたい。」(146頁) ⑪ 正しい発心 「発心正しからざれば萬行空し。」(158頁)(注:雑念混じりの信心は排すべし) ⑫ 無常に生きる 「真実なる自己の生命を挙げて発心して座禅するのである。道元禅師の只管打坐は処世術でも技術でもない。人格の真実である。無常ということは、生きることである。いかにして、真実の生活をするかの努力が仏道者なのである。なにかのまねであったり、つくりものであったりしたならば、そんなものは人間ごとであっても仏道ではない。仏道とは、いろいろな動きをする以前の、もとの自分になることなのである。」(159頁)(注:澤木禅師は、座禅は何にもならないと説きつつ、座禅に励んだ。) ⑬ ふがいない師匠 「わしのところへ小僧に来る者は、寺も、名誉も、金も欲しくないということでなければ駄目である。わしには、小僧に分けてやる寺も、金も、名誉もないし、わしに随身していても永久に出世しないだろう。世間的に考えればまことにふがいない、意気地なしの師匠である。」(200頁) ⑭ 一冊でも多くの本を 「一面から見ると、わしの一生は印刷屋や本屋へ奉公しながら、世の中に一冊でも多くの古仏の書をのこし、それが容易に、人々の手に入るようにあらしめたいと努力したに過ぎぬといってもいい。」(230頁)(注:澤木禅師の著者は多数あるが、すべて口述記録であった。)
2020年の3冊 :弓山達也
『科学化する仏教―瞑想と心身の近現代』碧海寿広著
『先祖祭祀と墓制の近代―創られた国民的習俗』問芝志保著
『宗教文化は誰のものか―大本弾圧事件と戦後日本』永岡崇著
初出:『佛教タイムス』2020年12月10・17日合併号
2020年の3冊を選ぶにあたり、30歳代の単著というしばりをかけてみた。評者は宗教社会学を専攻し、特に近現代の宗教やスピリチュアリティについて研究を進めてきたが、意外にもこの分野の異なる3つのフィールドから1冊ずつをあげることができた。
『スピリチュアルケア研究―基礎の構築から実践へ―』 窪寺俊之著:弓山達也
初出:『スピリチュアルケア研究』2(2018)
1.はじめに
著者の窪寺俊之先生と初めてお会いしたのは、2014年に評者が勤務していた大正大学で開催された臨床宗教師フォローアップ研修であったと記憶している。ペアワークがあって、ある報告者に対して厳しいコメントをされる先生に、自己紹介しようかどうか迷っていたところに声をかけていただいた。どうしてそうした話になったのか思い出せないが、スピリチュアリティと教団との関係の話題となり、「教団抜きの宗教性に可能性を見いだしていましたが、結局は根無し草になってしまう」ということを申しあげたところ、評者の覚束ない見解に、「その通りですね」と仰り、組織や場の重要性をご教示いただいた。先の厳しいコメントと相まって、このエピソードの後、窪寺先生の論考に触れる時には、常に「教団抜きにスピリチュアリティは成り立つのだろうか」という緊張感を孕んだ問いを反芻しながら読むようになった。
まえがき 第Ⅰ部 第一章 「宗教的思考」から「スピリチュアルな思考」へ 第二章 「スピリチュアル/宗教的ケア」の役割と課題 第三章 スピリチュアルケアと信力の一考察 第四章 祈りのスピリチュアルケア 第五章 スピリチュアルヒストリー法 第六章 〈信望愛〉法の可能性 第七章 「スピリチュアリティとは何か」をあらためて問う 第Ⅱ部 第八章 スピリチュアルケアと自殺念慮者へのケア 第九章 生きる意味を求めて 第十章 スピリチュアルなものへの魂の叫び 第十一章 スピリチュアリティと心の援助 あとがき 小生の関心を述べることが許されれば、本書は大きく分けて、宗教とスピリチュアリティ(1章、2章、10章、11章)、スピリチュアルケアの可能性と限界(3章、5章、6章、7章)、ケアの実践(4章、8章、9章)のテーマを発見できる。 2,宗教とスピリチュアリティ 最初のテーマである宗教とスピリチュアリティとの関係は、スピリチュアリティ研究の根幹をなすものだと思う。評者自身はかつてスピリチュアリティを「宗教教団から横溢する宗教性」とか、「宗教教団に依らない宗教性」とか、「無宗教の宗教性」などと説明してきた。しかし先にも述べたように、宗教教団、宗教儀礼、信仰を離れてスピリチュアリティは成り立つのだろうかという問いが本書を読んでいても頭をよぎる。第1章では、いわゆる苦難の神義論をベースにユダヤ教のラビでああるH.S.クシュナーが、その苦難をユダヤ教から、やがてその伝統的な神学を離れ、新しい神の理解にたどり着く過程が描かれている。そこでのキーワードは「宗教という枠に束縛されない「しなやかな思考」」となる。2章では高見順と原崎百子の日記を取り上げられ、がんとの向き合いを宗教的ケア、スピリチュアルケアから整理するものである。高見に代表される信仰なき現代人にとって、帰依を求める宗教的ケアは近づきがたく、自力の限界はあるものの多角的な援助を可能にするスピリチュアルケアが有効である。牧師夫人の原崎のばあいは信仰を梃子にした自己受容・他者関係・不条理への対処が可能になっている。こうした整理は第二のテーマであるスピリチュアルケアの可能性と限界とも重なってくる。 10・11章は講演原稿となる。10章では、著者は金子みすゞの詩「雪」を取り上げ、彼女のスピリチュアルな感性・思考法を抽出する。それは「お空」の神的存在の意思を感じ取れる感性だったり、「魂の故郷」に思いを馳せる思考法だったりする。続けてキリスト教の世界のもたらす恵みとして、苦難を誇りとして感じることや、神の愛は罪人にも注がれていると理解することが紹介されている。仏教的な世界観を背景としつつスピリチュアリティの世界を体現する金子みすゞと、キリスト教とを対立するものとしてとらえるのではなく、むしろ価値観を転換させる、あるいは拡充させるスピリチュアリティや宗教の可能性が述べられている。11章では宗教的ケアが「赦し」といった救いを、スピリチュアルケアが「癒し」を扱うと判りやすく解説。「ふるさと」「千の風になって」の歌詞から、後者の「癒し」の世界が示されている。 3,スピリチュアルケアの可能性と限界 宗教は永い時間をかけ、広範な人々の英知を傾けて、自らの救いの実践と理論を洗練させてきた。また多くの宗教は自らの無謬性や、他の宗教伝統と比して自らの優位性を説いてきた。しかし宗教から離れて、スピリチュアルケアを考える時、その可能性は自明ではなく、積極的にそれを明らかにすることが求められる。またスピリチュアルケアが医療・看護・福祉といった技術革新が日々進む分野と連携を取ろうとするならば、他領域との専門性や分野の棲み分け、そして自らの役割の限界をも見極めなければならない。そうした意味でスピリチュアルケアは常に自らの可能性と限界を表明する必要がある。そうでない限り、スピリチュアルケアが万能であるというような錯誤に陥る危険性が常に胚胎している。 3章ではスピリチュアルケアにおける「信じること」に注目する。著者はそれを「信力」と呼び、特に「信じるという行為」にスポットを当て、信仰・信頼・自信に分けて、その特徴・構造・機能・成果を解明する。5・6章はスピリチュアルヒストリー法に関する論文である。著者はスピリチュアルペインやニーズに関するアセスメントの必要性を述べつつも、それが患者の負担になることを指摘。そして患者や家族のスピリチュアルな生活の情報を集めるために開発されたスピリチュアルヒストリー法を紹介する。そこでは患者の信仰の有無、信仰の働き、宗教教団との関係、信仰と医療の関係、院外からの援助の有無が問題となっている。こうしたスピリチュアルヒストリー法は従来のアセスメントに比べると情報収集に優れているが、その分類や分析、定量化においては限界があることを指摘している。6章では、こうしたスピリチュアルヒストリー法の限界を踏まえて、著者は新たに〈信望愛〉法を提案する。「信」は信仰・信念・信頼、「望」は希望・期待・願望・欲望・夢・幻・頼み、「愛」は愛・愛情・友情・思いやり・いたわり・善意・好意・関心に関わる。これを通して患者の物語(ナラティブ)が引き出せるという。 7章は第Ⅰ部を閉じるにあたって、再度、スピリチュアリティとは何かの定義から始まっている。そして神仏のようなスピリチュアリティ本体と、それを認知する人間を結ぶスピリチュアリティ絆機能によってスピリチュアリティ世界が立ち上がるという。しかしスピリチュアリティ本体が第一にとなって人間がそれに従うという主客逆転が起きる危険性があることに、著者は警鐘を鳴らす。 4,ケアの実践 言うまでもなくスピリチュアリティを議論することやスピリチュアルケアは神学的・哲学的であるとともに極めて実践的な性格を持つ。しかもその実践の現場では、生命が今や消え入ろうとしていたり、希望が閉ざされたり、大切なものが失われたりする、緊急かつ厳粛な場面が出来することも少なくない。従ってスピリチュアリティやそのケアに関わる者は、それに見合った専門性と倫理性、深い洞察、思いやり、愛情が必要と考えられる。しかし同時に当該問題は広く多くの人にも開かれてもいる。高齢化が進む反面、医療は高度に専門化・複雑化し、患者やその家族が疎外される場面が生じやすくなっている。同様に社会において生活者が生きる意味や働く意義、友人や家族と過ごす価値を見いだしづらくなりつつある今、スピリチュアルケアは専門家の専有物ではないはずだ。むしろそのリテラシーは広く共有される必要があると考えられる。 4章では、キリスト教で用いられる他者のために/他者に代わって祈る「執り成しの祈り」を、信仰のない人にも敷衍できる可能性が示されている。そこでは患者とケア者が苦痛や希望を共有すること、患者が自分を越えたものへ気づくことや自分の内面と見つめることを促すこと、これらを可能にするケア者の人格的力が必要になるという。さらに著者はケア者には優しさ、感性、信仰、魂に届く言葉が求められると説く。 8・9章は講演原稿となる。8章では自殺念慮者へのケアとしてスピリチュアルケアが有効であること示される。著者によれば自殺の直接的原因は心理的狭窄にあり、スピリチュアルケアは自己執着・固定観念・既成概念からの解放をもたらし、狭窄した心を開く。そして自己・他者・未来の認識の回復、信じる能力の回復をもたらすとする。9章は著者の病院でのチャプレン活動の経験に基づき、一人のがん患者が不安と怒りから、少しずつ自らを語り始め、洗礼を受けるに至る過程が語られている。そして強がりの自分から解放され「この病気になってよかった」と語ったという。無宗教の患者が、時には宗教的な赦しを必要とし、スピリチュアルケアがそれを後押ししたケースといえよう。 5,再び宗教との関係から 各章を拝読して2点深く考えることができた。一つは冒頭にもこだわった宗教とスピリチュアリティとの関係であり、もう一点はスピリチュアルケアの自律性の問題である。 一般にスピリチュアリティやスピリチュアルケアに関する研究書は宗教的ケアとスピリチュアルケアとを明確に分けようとする。この姿勢は著者も同様で、『スピリチュアルケア入門』(第4章)でも、『スピリチュアルケア序説』(第5章第1節第4項)でも、『スピリチュアルケア概説』(1章2節2項)でも、両者の違いに注意を喚起、混同を戒めるセクションが設けられている。もちろん、この基本は揺るがしえないものの、本書の特徴は両者間の移動や相補性に紙幅が割かれている。第1章のクシュナーはユダヤ教からスピリチュアルな思考法に舵を切り、第10章の金子みすゞは仏教に帰依しつつ、スピリチュアルな世界を体現しえた。4章の「執り成しの祈り」、9章のがん患者の洗礼までの事例も、宗教的ケアとスピリチュアルケアの交錯する点が重要であると見ていい。ケア従事者に越境を慎むことが求められるものの、実際の垣根は低く、なだからであろう。 評者の体験からも、例えば被災地を学生と回る時(コーディネータをつとめていた)、南三陸町の防災庁舎のような多くの方がいのちを落とした現場では自然と手を合わす姿が見られる。ほとんどの学生は無宗教的あり、こうした無宗教の祈りの背後にスピリチュアリティを見出すことに大きな異論はないだろう。しかしその合掌を促したものは、祭壇であったり、仏教系大学ゆえ学生の中に混じる僧籍保有者の読経の声であったりしたことは間違いない。また評者は仏教系の路上生活者支援団体(ひとさじの会)に混じって配食活動に関わらせていただいている。夜回りの際、暖を取るうちに段ボールに火が燃え移り亡くなった方のいた高架では躊躇いなく念仏の声が起こる。参加者の多くは無宗教である。しかしそこには作務衣の僧侶の姿が決定的な影響を与えている。 宗教的な伝統によって育まれてきた感性、作法、場の雰囲気、慣習から離れて、虚空にスピリチュアリティのみが存在するとは考えられず、その相互関係、ケアの相補性、グラデーションに目配りが必要となることを本書を読んで再認識した。 6,スピリチュアルケアの自律性に向けて 既述の通り、本書の5・6章はスピリチュアルアセスメントとスピリチュアルヒストリー法に紙幅が割かれている。アセスメントの問題は『スピリチュアルケア入門』では触れられず、『スピリチュアルケア序説』(第10章)では、その意義を認めつつ、指標の不明確さと信頼関係が築けていなければ的確にスピリチュアルペインを把握することはできない危うさを指摘。これは『スピリチュアルケア概説』でも継承されている。そして本書では、さらに踏み込んでスピリチュアルヒストリー法、その中でも著者が開発した〈信望愛〉法が紹介されている。 エビデンス重視の医療現場にあって、ペインの個別性が高く、また癒しのプロセスが客観視しづらく、科学的な指標と馴染みづらいスピリチュアルケアが、ややもすると等閑視されたり、補助的な地位に追いやられたりする危険性がある。こうした中、エビデンス志向の医療(EBM)に比肩する洗練を目指すのではなく、むしろそうではない患者の物語に寄り添ったケアのあり方やその手応え・確からしさ(ある意味でEBMとは別のレベルの実証性)を担保しようとする課題は喫緊のものといえよう。『スピリチュアルケア序説』(第11章)ではナラティブ・ベースド・メディスン(NBM)への言及が見られる。著者の提唱する日本版スピリチュアルヒストリー法は、信頼関係を基盤に患者のナラティブを引き出す手法であるが、著者は科学的客観性の観点からデメリットも認めている。だが評者はむしろEBMのレベルでの科学的客観性よりも、NBMとして、その手法の標準化やデータ蓄積の精度が吟味されることを期待している。 いずれにせよスピリチュアルケアの資格・制度がその端緒についたばかりの日本において、今後、スピリチュアルヒストリー法のみならず、さまざまな方法や理論が検討され、やがて地歩を固めて行くに違いない。全人的なケアの現場の一角に、他領域のケアと協働しつつ、スピリチュアルケアが自律した地位を築くことが求められている。当該分野に先鞭をつけ、斯界を牽引してきた著者の最新書を前に、私たちはさらに議論を重ね、スピリチュアルケアの学として、実践として、その自律性を追究してかねければならない。
『グリーフケアの時代「喪失の悲しみ」に寄り添う』 島薗進・鎌田東二・佐久間庸和著:秋丸知貴
「週刊読書人」2019年11月29日
狂天慟地( きょうてんどうち ) 』